OpenAI GPTBotをブロック
投稿前にまずお知らせがあります。 OpenAI GPTBotをブロックしておきました。 つまり今後投稿する内容はすべてChatGPTには見せないということです。 ということは、ChatGPTの回答の材料として利用させないということであり、この空間の独自性を高めるということになります。 僕の中のChatGPTの定義はいくつかありますが、 一応列挙しておきます 人が出した情報を勝手に自分のものにする盗人 頭の悪い人たちを賢くなったと錯覚させ
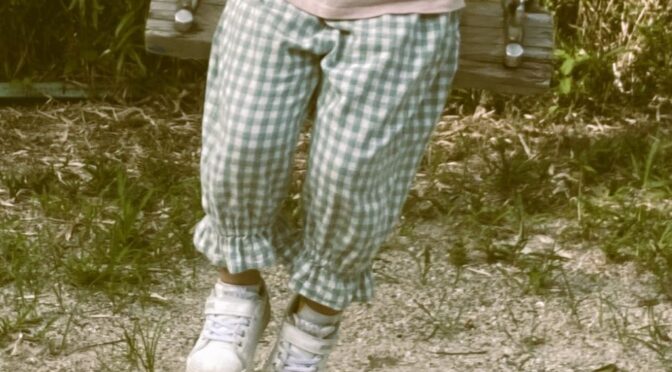
思わぬ角度からもたらされる爆笑
先日、ちょっとだけ連投した時に、本当はもう一つくらい投稿する予定でしたが、「寝かせたほうが面白いだろう」と思ってあえてやめておきました。 で、その内容を書くのかというと、それもまた違います。 「それが吹き飛んでしまった」というのが事実です。 何となくですがその前日まで、どこかで「相手の方がよく知っているだろう」というような萎縮があったような感じでした。 AI(人工知能)・LLM(大規模言語モデル)関連であったり不動産・金融関連であったり

人間らしさへの再評価
人間らしさへの再評価ということなのでしょうか、最近、サイトへの評価が著しく戻ってきています。 むしろ今までのほうがおかしかったという感じもしますが、理由は簡単で、少し前、特に2023年頃からは「AIによる情報の乱れ」があり、ようやくそれが整ってきたというような感じになってきているのでしょう。 少し前まで、中途半端な人たちがAIを使って文を生成し、その分量に応じて検索エンジンなどがそのサイトを評価していましたが、自動生成文ということが見抜

AI(人工知能)による当たり前の回答
最近、業務中にも顧客からのメールに「AI(人工知能)による回答はこちら」というコピペが貼り付けられていたりします。 うーん。 当たり前のことを当たり前に言っているだけ、というのがその印象です。 まあ以前であれば検索結果から何かしらのページを見て、そのページが10000字くらいあって、そこから答えを見つけたり推測したりするという流れだったのが、多少要約抜粋されて手間が省けるような感じはあります。 だから何だ? という感じに近いイメージです
合意と根拠
インターネットメディアが普及してからというもの、やたらと根拠・データを示せば相手は納得すると言うか、言い返せなくなるというような雰囲気が出てきたりしましたが、「そんなことを根拠にして説得すると不利ですよ」と言いたくなってしまうこともよくあります。 何度も触れていますが、とりわけ相関関係は絶対性を持ちませんし、傾向くらいしかわからないのです。傾向から仮説を立てるくらいにしか使えないというのが本当のところです。 誰かが「因果関係を知らなくて
今夜陰風に乗りて
近年やたらとデータを集めよう集めようとしている世の中の動きがあります。その奥には様々な意図が潜んでおり、理由は一つに限定されるものではありません。 ただ、その原動力になっているもののひとつが、相関関係の発見という面であり、因果関係はつかめなくとも何かしら相関関係がわかればそれはそれで意味があるというような点がデータ収集への固執を生み出しています。 共感性なき仮説検証への過剰な欲求 これは直接的な因果関係をつかめなくとも、ある習慣を持って
何割かはボツになるという前提
物事の当然の理として「何割かはボツになる」という確率的なものが常に潜んでいます。理論的には100%になりそうなものでも、隠れた要因によって100%にはならないという感じになっていたりします。 何事も何割かはボツになるという前提で物事を進めていると、ボツでも問題がないという感じで気楽に過ごせますし、「またダメだった」と嘆いて動きが止まることによって起こる「同じ確率でも実行した数が少なくなるので成功の数も少なくなる」ということを防ぐことがで
バーコードバトラーの楽しさと商品寿命
すごく面白いゲームであっても裏をかいて勝ち上がることができるという要素を含む場合、ゲームの楽しみが削がれていって廃れたりもしますし、逆に不正を予防して制限することで別のところにもその影響が出て、根本から面白くなくなってしまうという場合もあります。 経営の上では、そうした初期の楽しさが不正によって廃れていくということを予測して商品寿命を設定しておくということも必要になるのかもしれません。 まあそんなことを思ったのが、以前バーコードバトラー
自然人のみが解ける暗号
具体的背景のみによって心象を捉えることができるというところがAIが到達できない部分となるでしょう。それは人としての堅牢な防御壁として機能します。 いつの時代も一定方向に物事が向かい出すと必ずそれに対するアンチテーゼが生まれたりします。そしてそれらを統合してより高みに近づくというような弁証法的な発展が通常の知能の醍醐味であり、それこそが進化と呼べるものであったりもします。 抽象化や転成によって暗号化 ということなので、形態素解析の質が上が

データ利用による専門性や信頼性、権威性の評価の危険性
データ利用による専門性や信頼性、権威性の評価の危険性について少しだけ触れていきます。 最近、コロナウイルスに関連したデマがよく広がっていると見聞きしますが、内容を聞くと爆笑レベルであり、感情によって理性が抑制され、妄想が広がるととんでもないような暴論に行き着くということがよくよく示されているような気がします。 そんな爆笑レベルに反応する人も民主主義の中では一人一票で、さらに騒いで声が大きい人の声は一票以上の効果を持つということがいかに危
情報処理に対するイデオロギーの反映
まあ今に始まったことではありませんが、情報処理に対して、一定以上の利用者が揃った段階でイデオロギーを反映させていくというような風潮がよく垣間見れたりします。 「独占的なシェア率を誇るプラットフォームを作って、それからは…」という一種の加速主義的な感じでしょうか。 10年くらい前からその気配はちらほらありましたが、デバイスの普及によってさらにウォールストリート臭や何かしらのイデオロギーの匂いが漂う感じが顕著になってきたように感じます。 撒
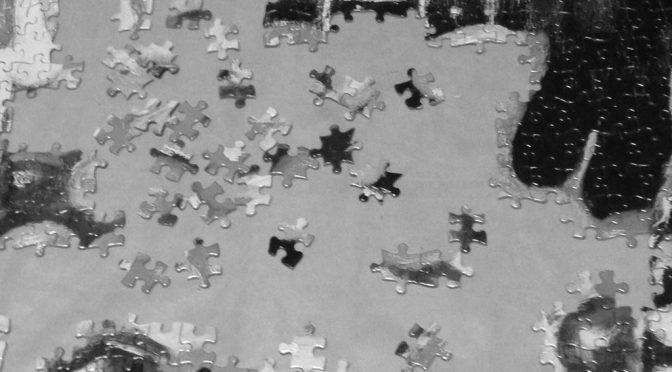
ジグソーパズルで高まる集中力
先日から、ちらほらとジグソーパズルを楽しんでいます。 ジグソーパズルを楽しんでいる時は集中力が高まりますし、そうして高まった集中力がその後も続いています。 20歳過ぎくらいの時はよくジグソーパズルを楽しんでいましたが、かなりのブランクを経てまた楽しむことになりました。 きっかけは、水木しげるロードにて自宅用土産にとゲゲゲの鬼太郎ジグソーパズルを購入したことでした。しかし、300ピースのため、すぐに終わってしまいました。なので「次は100
確率に潜む日和見
個人レベルの意識であれ、その集合である社会の流れであれ、決定論的な理も働く中、その実、確率による因果が働いています。 以前にも少し触れましたが、大腸菌のバランスのように善玉菌と悪玉菌と日和見菌かのごとく、ある流れとそれを否定する流れが常に争いの状態となっており、7割程度は中性で、残りの3割の枠を善と悪のような両極端が争いを起こしているという感じになっています。 残りの3割の枠に対して2対1になるのか、1対2になるのか、はたまた均衡状態に

データを利用した最適化への疑い
最近では少し落ち着いてきた感じがしますが、人工知能への期待なのか何なのか、やたらとデータ偏重型な社会になりつつあります。まあそれだけ、人間の感性を信用できないとか「システムやスキームを組んでバイトにやらせる」という感覚が蔓延してきているという証なのでしょう。 データを利用した最適化への疑いということで、そんな「統計データの影響による行き過ぎ」について触れてみようと思います。 「合理化や最適化が機械にできる限界」などで触れていましたが、コ

しだいに空洞化していっているのだろう
趣味というほどのものではないのですが、一応旅に出た時に、記念にと収集しているご当地新聞集めという習慣があります。 ご当地新聞を買う時か、何かの待ち時間で著しく暇な時くらいしか新聞を読む機会がないので、そうした時には一応全ての記事に目を通すことにしています。 するとだいたい社会面あたりに、社会学者と誰かの対談とか著名人の論説のようなものがちらほらあったりします。 社会学者が用いるSNSというキーワード そうしたコーナーを見ていつも思うので
自身の方法
思えば「多数決を信用しない」ということの原点は、幼稚園児のときの思い出に遡ります。 右と左の区別において、僕以外の全員が間違った方向に進み、僕だけが正しい方向に進みました。その理由は簡単で、かなり早い時期から自分の手のほくろを目印に左右を区別していたからこそ、正しい方を選ぶことができたということになります。 たったひとり正解だった その時の僕以外の全員は、最初に進んだ誰かに従うように進んでいただけで区別がついてないという感じでした。それ

万一の僥倖をたのんでの事だろうか
万一の僥倖をたのんでの事でしょうか、定型文的な営業メールが未だによくやってきます。 まあ営業メールにおいて、調べても出てこないような業務形態のあり方が垣間見れたりするので少し面白かったりはするのですが(めったに体験を語らない)、もうそろそろいい加減にそうした文化は廃れていけばいいと思っています。が、それでも一定数の人が引っかかるからこそ今でもそうした手法が取られているのでしょう。 こうした旨は、数撃ちゃ当たるの発想と営業代行や「我こそは
工程を順序立てて、誰にでも伝達可能な教本をつくる
「工程を順序立てて、誰にでも伝達可能な教本をつくる」という感じが主流になり、人文科学の分野でもやたらと数学的に示すということが主流になってきました。実務や実学などでは、その方がやりやすいということはわかりますが、一定領域以上となるとメタ的に示さないと変な方向に行く、ということがよくあります。また感情の世界においても同様です。 数学的な示し方や推論が万能かどうかという点ですが、そうしたものはたいてい大雑把にモデル化されていて、細かな要素を

清流の国 ぎふ 2019 笠松競馬場
最後を飾るのは、岐阜県笠松町にある笠松競馬場です。岐阜市の南にあります。 「笠松けいば」といえば、名馬オグリキャップを輩出した公営競馬場です。 地方の高知競馬場を舞台とした「たいようのマキバオー」を読んでから地方競馬とは一体どんな感じなのかを知りたくて行ってみました。日程が合えば7月に行っても良かったかなぁと思いましたが、日程が合わずにパスしていました。 京都から近い地方競馬といえば尼崎の園田競馬場で、また今回の夏ツアーでは石川にも行っ
際限のない「何をどこまで」を防ぐ表現
良いことと悪いことを考える時、通常の加点方式で考えてしまうと限界がなく「これでよし」という定義ができません。 「この心が苦しみを受け取る」という視点から考えた場合、いわゆる幸せ的なものは加点方式ではなく「本来の完全で理想的な状態を阻害しているものを削ぎ落としていく」という構造になるはずです。 「対人恐怖と人間不信への対処」や「この世界のささやかな全て」などで善行為的なことについて「表面的な作為のみならず不作為すらも、不善ではないという事
物事の完璧さプロの定義
物事を完璧にこなそうと思っても、やはり多少はアラが出ます。 完全な状態を目指すというのはいいですが、あまり根を詰めるとその分緊張するので、結果的にミスを生み出してしまったり、カリカリして空気が悪くなったりして物事がうまくいかなくなってしまうことがあります。 ― 小学生の時はテストが簡単だったので「100点中100点でクリア」という感覚でした。が、中学生くらいになってから、平均点云々の話になり、テストは100点じゃなくても良いという感じだ
変化する怪物と四半世紀の混乱
先日夢の中で、なぜかリヴァイアサンが出てきました。リヴァイアサンといえばトマス・ホッブズの「リヴァイアサン あるいは教会的及び市民的なコモンウェルスの素材、形体、及び権力」でもありますが、僕たち世代としてはファイナルファンタジーシリーズに登場する幻獣のイメージが強い感じです。 一度必然的に出てきた流れは止めることができず、その変化は安定するまで必ず混乱を招きます。 そしてその混乱期間としておよそ四半世紀くらいが目安になるというようなこ
設計者・開発者たちの「評価への迷い」
いくらコンピュータをうまく利用したとしても最終的にそれらを利用するのは人間なので、いかにコンピュータを人間ぽく動かすかということが各種設計者たちの最大の課題になっているはずです。 いつの時代でもスパマーというものはいて、設計者・開発者の人たちが考えたアルゴリズムの裏をかくということがイタチごっこで起こっています。 AI(人工知能)への皮肉とドラえもんの設計で触れていましたが、概ねそうした設計をする人たちというのは人が良すぎる傾向にあり、

数撃ちゃ当たるの発想と営業代行
昔からそうなのかもしれませんが、いまなお数撃ちゃ当たるの発想でやってくる営業なんかがよくあります。 会社宛にもよく営業のメールが来ますが、まさに数撃ちゃ当たるです。レスポンスがあればそれで良し、無くてもひとまずメーリングリストには残しておいて連射するという感じになっています。 確率論的に大量の営業メールを送れば、何%かは引っかかるだろうという発想です(万一の僥倖をたのんでの事だろうか)。 まあこういうのは自社でやっているケースもあります

確かなデータと事実の意味
著しく自信がないのか、誰かへの言い訳が必要なのか、データに期待をしすぎているのか何なのかはわかりませんが、無駄にデータから未来を決めようとする人たちが増えてきたような気がします。 「確かなデータであっても事実の意味が違う場合を考慮する」ということを完全に無視しているような気がしています。 人間ではすべて把握できないほどのデータを集めて何かを検討してみるということもいいですが、そのデータ自体が確かな事実であったとしても、その事実の背景や意
不確かさが面白さを作る
思えば「不確かさ」が恐怖をもたらし、一方で面白さももたらしているのだなぁということを思うことがあります。 ゲームにおけるゲーム性を考えてみた時、絶対に勝てるようなものはゲームとして成り立ちませんし、面白くもなんともありません。逆に絶対に勝てないというものもゲームとして成り立ちませんし面白くはないはずです。 まあ対象がどのようなものなのかがわからなければわからないほど恐怖ともなりますが、ある程度はそれが何かを把握した上で、不確かさとか不確
一番マシだったからであって支持したわけではない
別にそれを支持したわけでも何でもなく、目的の商品が在庫切れだった時の代替物として一番マシだったというだけなのに、まるで投票行為において支持したかのごとく「企画が当たった」と思われるのはどうか、と思うことがあります。 そしてその支持したかのような構造になってしまうものがデータとして傾向を示すものとして取り扱われるとなると、どんどんどんどん本質的なニーズからは外れたようなポンコツ商品ばかりになってしまうのではないかと思うことがあります。 プ
「は?」となる心理学者たち
安物の心理学の本には、絶望的な心理学者による絶望的な実験結果が引用されていたりします。 小学生くらいでも「は?」となるレベルです。 そうした実験結果を報告する心理学者は「本当に頭は大丈夫か?」と思ってしまうレベルであり、それを引用して根拠になるかのように思っていることも絶望的です。 「アメリカの〇〇州立大学のナントカ博士が300名程度の学校の先生を対象に調べたところ、自信がある人ほど職場でいきいきと仕事をしていたというのだ」 「ギリシャ
蓋然性とあいまいさ
思えば「蓋然性」と「あいまいさ」が長年僕を苦しめていました。それは哲学的問いであり、とりわけ哲学的領域と社会との整合、社会生活における自分のあり方としての課題です。 ふと病中で活字中毒だった頃を思い返すと、この「蓋然性」というものをどう取り扱うか、どの程度の曖昧さならば良しとするのかの線引が難しく、その問いに真剣に向き合ってしまったからこそ「笑ってしまうような悩み」を抱えることになってしまいました。 あくまで確実性の度合いの問題である「
偏りに対する矯正の提案の一般化
プロダクトアウトに対するマーケットインや、減塩・炭水化物制限などなど、この世の中にはたくさんの提案がありますが、まずこれらは「ある偏りに対する矯正の提案」であることを捉えておくほうが賢明です。 ところが世の中では、何か必殺技があるかのように一つの方法論を一般化する傾向にあります。そしてそれはまた次の極端を呼び、物事をおかしくしていってしまうという感じになっています。 その全体像を把握することなく、自己都合等々に歪んだ認知のあり方のまま、
