
ほんの少しの旅に出よう
一人旅は非常に良いものです。 で、家に引きこもっていて寝たきり状態になっていても、もう十分に身体は現時点の限界まで休まっているので、それならばいっそほんの少しの旅に出てみましょう。 予算は1000円か2000円位でどうでしょうか? 僕はそんな低予算の旅によく出掛けました。 21歳か22歳位の頃です。 それでは、それくらいの時に出かけた旅の様子をご紹介していきましょう。 少しの準備 当時は携帯電話のカメラ機能も大したものではなかったので、

新年 2018
みなさま、あけましておめでとうございます。 2018年になりました。 早速白味噌の雑煮で杵つき餅を5つ食べました。 新年ということでひとまずは抱負のようなものを書いていきます。こうしたものを普段あまり意識することはありませんが、あえて意識してみましょう。 新年の抱負 2018年新年の抱負ですが、まずはもう少し間口を広げるためにということを含みつつ、少しはモテてみようかなぁという感じです。 これは、つい先日年末ということもあって、X JA

さよなら2017
さあもうすぐ2017年が終わります。 一応2017年を少し振り返っておきましょう。 急に仕事のやる気が無くなったり、養子が死んだりということもありましたが、急に大掛かりな仕事が舞い込んできたり、急に沖縄に行っていたりと、急な展開がよくありました。 最も大きな変化は養子のうさぎが亡くなったことですが、それは彼の死と同時に彼と出会う前の僕の意識との再会があったことも含まれています。 思えば我が家にうさぎがやってくる少し前の僕は、毎日が楽しか
哲学と解釈
哲学することと哲学を学ぶことは大きく異なり、また哲学することと解釈することは大きく異なっています。 ではそれらは何か違うのでしょうか? その根本的な違いは、ある具体性を持ったものの内側を見ようとすることと、具体性を突き抜けて、より抽象化していくことにあります。つまり、具体性を包括しつつより全体的で統合された地点から自己解釈を再構成するということです。 特別企画の曙光(ニーチェ)完了記念ということで、何かニーチェっぽいことでも書いてみよう
隣人を愛する前に愛を思い出しなさい
「隣人を愛する前に愛を思い出しなさい」という謎の命令形タイトルになっています。一応新約聖書にちなんでいますが、特にそうしたものの解釈について触れてるわけではありません。 うつを治そうというようなテーマで語られる時、自分の殻に閉じこもらずに他人と接し、他人を愛しなさい的なことが言われることがあります。「自分を愛するように隣人を愛しなさい」というようなやつです。 それはそれでいいのですが、単に他人を愛そうと思っても十中八九失敗に終わっている
見渡せば秋冬生まれの文化系
12月です。僕は12月生まれです。 見渡せば秋冬生まれの文化系ということで、昔からずっと秋冬生まれの友人が多く、文化系の人ばかりが友だちです。 ほとんど11月以降に誕生日を迎える人ばかりが友だちで、そしてなぜか10月生まれに特に仲のいい人はいなくて、飛んで9月生まれに友人が多いというのも不思議です。 まあその理由に関しては小学生の時から薄々感づいていました。 学年の最初の方の月に生まれた人は体育会系が多い 同学年のうち、学年の最初の方の
モテる秘訣とモテない理屈
さて、モテる秘訣とモテない理屈について書いていきます。 世間では様々なモテテクやモテるための条件、モテる秘訣、そしてモテない理由としての理屈が並べられています。 しかしながら、そういうものを鵜呑みにしてしまうと、婚活業界、結婚相談業界のお客になってしまうだけです。 どのような分野でも同じですが、具体的な事例自体を知ること自体はいいですが、そんな具体的な領域にとどまっていると、そのレベルの内側に居続けることになります。 そんな浅い領域から
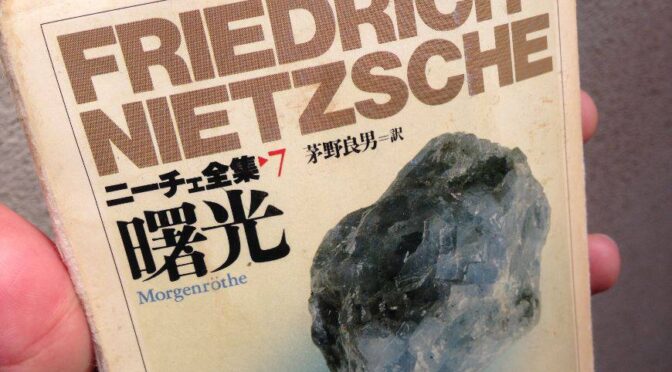
曙光(ニーチェ)
ちくま学芸文庫より出版されているニーチェ全集7「曙光」の各節題目表よりタイトルを拝借し進めてきました特別企画「曙光(ニーチェ)」がついに全て完了しました。 本シリーズは575項目ありますので、投稿数はすごい量になっています。ということで一覧ページを設けておきます。 曙光 第一書 曙光 第二書 曙光 第三書 曙光 第四書 曙光 第五書 「曙光(しょこう)」とは、夜明けに差してくる太陽の光を意味します。暗い夜から一筋の強烈な光が差し込んでく
われわれ精神の飛行する者!
しかしそこから、それらの前には巨大な自由がもはや全くないとか、それらはわれわれが飛ぶことの出来る限り飛んだとか、推論することがだれに許されようか!われわれの偉大な師や先駆者たちもすべて最後には立ち止まった。そして疲労で立ち止まるのは、極めて高貴な身振りでも優美な身振りでもない。私も君もそういう成り行きになるだろう!しかしそれは私にとっても君にとっても何の関係があるだろうか!他の鳥がさらに遠く飛ぶだろう! 曙光 575 一部抜粋 この「わ
他人を喜ばせる
人を喜ばせることはなぜすべての喜びにまさるのか?― われわれはそれによって自分自身の五十もの衝動を一度に喜ばせるからである。ひとつひとつのものは極めて小さな喜びであるかもしれない。しかし、もしわれわれがそれらすべてをひとつの手の中に入れるなら、これまでかつてなかったほどわれわれの手は一杯になる。― そして心も同様である!― 曙光 422 人を喜ばせる最たるものは、自分が喜ぶことです。 人が喜んだところを見て喜ぶのが正しいのであれば、他人
道徳に対するドイツ人の態度
ほかならぬこの民族に満足を与えるのは、いかなる道徳であろうか?たしかにこの民族は、その心から服従癖が道徳の中で理想化されてあらわれることをまず望むであろう。「人間は、無条件的に服従することの出来る何ものかを持たなければならない。」― これがドイツ的な感覚であり、ドイツ的な首尾一貫性である。人はすべてのドイツの道徳学的の根底においてこれに出会う。 曙光 207 中腹 一部抜粋 なんだかんだで、いまだに明晰夢のようなものをよく見ます。寝る前
「この印において汝は勝つであろう。」
その他の点でヨーロッパがどれほど進んでいようとも、宗教的な事物については、ヨーロッパは古代のバラモンの素朴な囚われない心にまだ到達していない。 ― さしあたりわれわれは、インドで、思索者の民族の間で、すでに数千年以上前に思索の命令として実行されたものを、ヨーロッパが取り戻すように気をつけよう! 曙光 96 一部抜粋 ニーチェによる「曙光」一書の締めくくりは、インドにおけるバラモン、そしてブッダの記述が見られ、ヨーロッパにおける心に関する
忘れるな!
われわれが高く上昇すればするだけ、飛ぶことの出来ない人々にとっては、一層われわれが小さく見える。 曙光 574 世間の人は客観的データによって人や物を相対的に判断しています。だからこそ広告物などにおいて、データや権威が役立つのです。 何の肩書も持たない人が、何かを話し出すよりも、大学教授という肩書を持った人が話すほうが耳を傾けられ、信憑性が高いという風に判断されるという感じです。 それはひとつの偏見であり、人を盲目にしてしまうものですが
遠くへの展望
よく定義されているように、他人のために、しかも他人のためにのみなされる行為だけが道徳的であるとすれば、道徳的な行為というものは存在しない! 曙光 148 序 人生設計やキャリアビジョンというような概念がありますが、そうしたものが語られていると知った時、なぜそうした狭い枠組みの中で夢を見させるのだろうというようなことを思いました。 以前、子供に将来の夢を聞くことは、ほとんどの場合その人の潜在可能性を潰すというようなことを書いたことがありま
他人を通して
他人を通してちらちら光る以外には、見られることを全く望まない人間がいる。そしてこれには深い思慮がある。 曙光 421 他人を通して自らを高めようとすること、それほど醜いものはありません。 例えば、学校か何かで一番の成績を取った人が「僕が、僕が、僕が、一番なんだ!僕が一番なんだ!僕ってすごいよね?みんな僕をもっと褒めてよ!」と連呼している人がいたとすれば、その姿は美しく見えるでしょうか? 「ひとりでやっておけ」 そんなことを思うのではない
最終的な反駁としての歴史的反駁
昔、人々は、神が存在しないことを証明することを求めた。 曙光 95 序 西洋的な方法論は、論理的な証明をやたらとしたがりますが、最終的に行き着いたポイントをよくよく見渡してみると、世界各国の土着の伝承、民話に隠されたメタファーと同じだった、というようなことがよくあります。 アメリカなどの最新研究の成果としてよく騒がれているような、哲学的な分野や認知科学の分野の方法を見ても、「そんなことは数千年前から既に説かれている」というようなものが多
不可能な階級
貧しく、楽しく、そして独立的!― これは一緒に可能である。貧しく、楽しく、そして奴隷!― これも可能である。― そして私は、工場奴隷制度の労働者たちにとってこれ以上よいことは言えない。 曙光 206 序 階級として有名なものはカーストです。そのカーストを紐解いてみれば、単にインド・ネパール地域に侵略してきたアーリア人が自分たちをバラモンとし、現地民をスードラとし、その混血をクシャトリヤやバイシャとしたのが始まりだとされています。 人とす
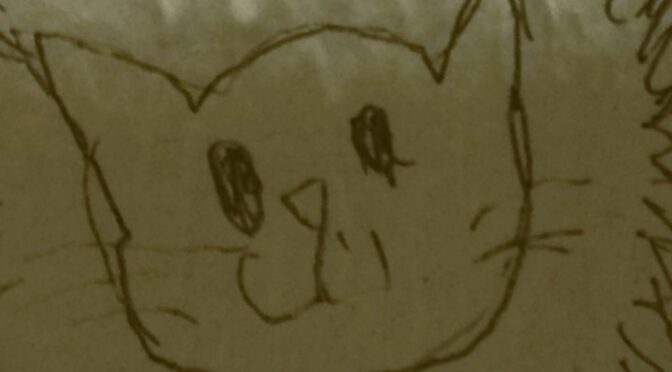
4歳児に教えてもらった素敵な言葉
先日、お客さんのところに行ったときに、その人の息子である4歳児に教えてもらった素敵な言葉があります。 いつもいつも「大学教授が言おうと幼稚園児が言おうと本質は変わりなく、言葉が指し示す意味のみを検討するべきだ」というようなことを言っていますが、まさに幼稚園児から教わることになりました。 意味は状況の中にある、ということにはなりますが、大体どのような状況においてもかなり良い感覚を呼び起こすフレーズです。 何気ない言葉ですが、いい言葉だなぁ

大峯山(大峰山・山上ヶ岳)2017
ひとことで触れていましたが、先日奈良県吉野郡天川村にある大峯山(大峰山・山上ヶ岳)に行きました。日本で唯一の女人禁制の山です。 基本的に登山のシーズンは5月から9月であり、山頂の大峯山寺も閉まっているような季節です。なお大峯山寺は世界遺産に登録されています。 約十年前の夏にこの山に登り、西の覗きと言われる崖に吊るされる修行などをしました。 そして、養子のうさぎが亡くなったこともあってか、なぜか養子と出会う以前の意識が舞い戻り、この場所に
不機嫌な人々の治療法
すでにパウロは、罪に対する神の深い不機嫌が取り消されるためには犠牲が必要である、という考えであった。それ以来キリスト教徒たちは、自分自身に対するその不快を、ある犠牲にむけて洩らすことをやめなかった。― それが「世界」であろうと「歴史」であろうと、「理性」であろうと、喜びであろうと、他の人々の安穏な平和であろうと― 何らかのよいものが彼らの罪のために死ななければならない(姿においてだけであっても)! 曙光 94 不機嫌な人々を見ると、その

第1100回投稿記念
これで1100記事目になります。1100回目の投稿ということで「第1100回投稿記念」です。 ZERO STAGEで少し嵩増しされた感はありますが、前回の第1000回投稿記念は、2017年9月20日で、前回からの100記事は、その前と同じくまあまあの速度で投稿したという感じです。 そういえばもう少しするとロングラン特別企画「曙光」が終わります。どうせならということで、題目終了後も多少注釈ページや「訳者あとがき」などからエッセンスを見つけ
脱皮する
脱皮することの出来ない蛇は破滅する。その意見を変えることが妨げられた精神の持ち主たちも同様である。彼らは精神であることを止める。 曙光 573 「脱皮する」ということで、人の成長について書いていきます。 十代の頃は、小学生から中学生、その先は人によりますが、高校生や大学生などになったり、働きだしたりと、その度に何となく違った世界が広がっていって成長しているような感じになります。 人間で言う脱皮という表現に当てはまるのが、世界の見え方です
生贄の狡猾
身を捧げたある人から欺かれようと思い、そうであってほしいとわれわれが望む通りの姿をわれわれに見せざるを得ないような機会を彼に与えるのは、悲しい狡猾というものである。 曙光 420 犯罪者や自殺者などは、現代における生贄のようなフシがあります。 ある人が見栄のため欲のためにしたことが誰かを傷つけ、その傷ついた誰かは怒りのためにまた誰かを傷つけ、そうしているうちにある人は理性の限界を超え、犯罪や自殺というようなことにたどり着くのだと思ってい
「利他主義」の原因
人間は一般に、愛を少ししか手に入れたことがなく、この食物を飽きるほど食べることができなかったので、愛を極めて強調し、偶像化して語ってきた。 曙光 147 序 「利他主義」の原因ということですが、利他主義はもちろん利己主義の対義語としての概念を持っています。利他主義とは、自分のことよりも他者の利益のことを考えるというような主義になりますが、本質的には別に自分を蔑ろにしてまで利他的であれというわけではないと思います。 しかし極端な利他主義と
イスラエルの民族について
ヨーロッパのユダヤ人の運命の決定は、次の世紀がわれわれを招待してくれる演劇のひとつである。 曙光 205 序 一応イスラエルはユダヤ人の国です。で、エルサレムはユダヤ教徒区画とキリスト教徒とイスラム教徒区画があったりします。 日本国内ではキリスト教以外のアブラハム系の宗派について、ほとんど認識がありません。だからその共通点も相違点もあまりわからないまま、ニュースなどで雰囲気だけ伝えられ、感情的に嫌だと思っているというのが本当のところでし
十七歳の地図
僕は1983年12月生まれです。 で、面白いのが、尾崎豊氏のデビューアルバム「十七歳の地図」が出たのが、1983年12月です。日までは同じじゃないですけどね。 僕が17歳の時、十七歳の地図も17歳です。 そして、それから17年経ったのが今日です。 で、2017年だったりします。 と、たったそれだけのことですが、数奇なものだなぁと。 ― これだけはっきり包み隠さずまっすぐに曲を作る人がまた現れたらいいですね。 改めて聴くと、そのメッセージ

閃光少女
一眼を持つ手があどけない。 一目見た瞬間に「これだ」と思った。 閃光少女だ。 ― 肩で息をしたい。 だから、 一枚でいいから彼女を撮りたい。 が、 仕事柄、毎日人とたくさん話しているせいか、「休みの時くらい話したくない」という病がなかなか治らないので、思わず帰って閃光少女を弾いてしまう。 ついでに透明人間も弾いてしまう。 再び坊主にしました。 (2011年06月13日01:09) 関連しているかもしれない記事です: ハイブリッド レイン

車の本「ゼフィラム」
リハビリをするために、小説を読むべく図書館に向かった。 楡周平の本があったので借りてみた。 「ゼフィラム」 表紙に車が載っていたことから、「自動車産業だな」とは思いつつ、 「あまり興味ないな」とも思いつつ借りてみた。 車が嫌いなわけではないが、むしろ運転は楽しいが、都市部に住むと費用対効果が薄すぎる。 なのであまりご縁がない車についていい機会なので考えてみる。 ついでに金融工学と言う博打×詐欺についても考えてみる。 さらに氾濫したモノと

連休(2011/5)
ありふれたようなタイトルだが、変な感覚が漂うのだ、連休と言う語に対して。 一週間ほどの休みと言うのはなかなか久しぶりかもしれない。 2連休か、3ヶ月と言う極端なものしかなかったからだ。 と、言っても明日は仕事。 … 弟の口から「ニーチェ」と「サルトル」という単語が出てきたので、明後日からは堀江氏のように、本を読もうかと思う。 この一年、自己主張することを控えてきたが、改めて「金髪にしたい衝動」のような自己主張願望が沸き起こってきているの

営業の師匠(仮)との思い出
営業の師匠(仮)との思い出について触れていきましょう。 基本的に全分野において師匠と呼べるような人はいませんが(習い事の先生や学校生活における恩師等々は一応います)、この営業の師匠(仮)については、短期間ですが営業について深く学び、影響を受けたと思っています。 師匠っぽい人。いや、師匠かもな 個性が強い僕ですので、師匠はいないのですが、それぞれある方面にのみ特化した「部分的な師匠」はたくさんいます。 こっちの準備ができた時に師があらわれ
