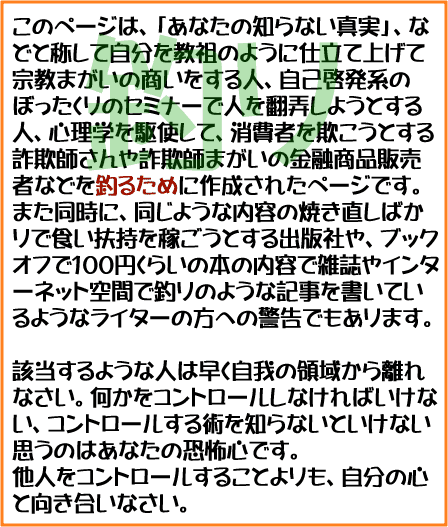
アブニー効果(Abney’s effect)とは、実際の色の見え方は、彩度の低下とともに変化する現象のこと。理論的には、ある特定の波長の単色光(色光)に白色光を混色すると、その白色光の量に応じて色光の彩度のみが低下し、色相は変わらないと考えられるが、彩度の低下とともに色の見え方自体が変化してしまうことを指す。
実際の色相は変化していないはずであるが、彩度の変化によりそれを見る人間の目には色相が変化したように見えるというのがアブニー効果である。
アブニーの法則
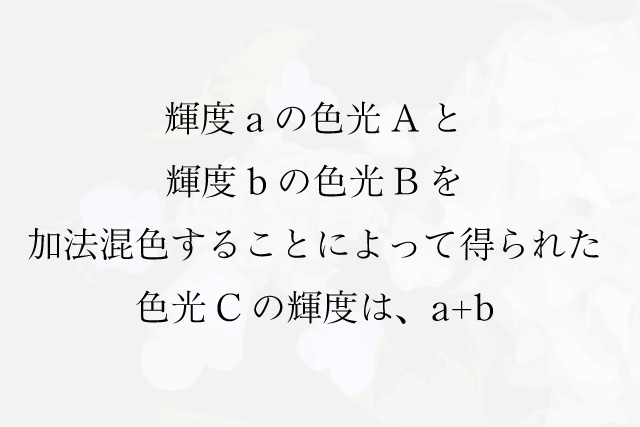
アブニーの法則
アブニーの法則(グラスマンの法則 第四法則)とは、加法混色における輝度の加法則で、「輝度(きど)aの色光A」と「輝度bの色光B」を加法混色することによって得られた色光Cの輝度は、a+bになる輝度の加法則のこと。グラスマンの法則の第四法則とも呼ばれるが、この加法混色における輝度の加法則を確認したアブニ氏ーの名からアブニーの法則とも呼ばれる。
知覚的色相の非線形性と現代色彩工学における課題
物理的等価性と知覚的乖離の発見
1910年にウィリアム・アブニーによって報告されたこの現象は、色彩科学における「波長」と「色相」の単純な等価関係を否定する転換点となった。物理的な主波長(Dominant Wavelength)を固定したまま白色光を加えて彩度を低下させると、知覚される色相(Hue)が変化してしまう。
これは、ヒトの視覚系が物理刺激をリニアに処理していないことの証左である。通常、光を混ぜ合わせる加法混色においては、Grassmanの法則に基づく線形性が期待されるが、アブニー効果はその限界を示している。例えば、特定の赤色に白色光を混ぜてピンクにする際、物理的には同じ主波長であっても、知覚的にはわずかに青紫寄りへと色相がシフトして感じられる。
生理学的メカニズムと反対色応答
現代の視覚生理学的な解釈では、この効果は網膜以降の神経節細胞や外側膝状体における「反対色チャンネル(赤-緑、青-黄)」の非線形応答に起因すると考えられている。
白色光の付加は、S・M・Lという3種の錐体すべてを刺激するが、それが反対色信号に変換される過程で、各チャンネルへの寄与率や飽和特性が均等ではない。彩度の低下(白色成分の増加)が神経信号のバランスを崩し、結果として脳が解釈する色相の角度を歪めてしまう。特に、色空間上で黄色や青色の近傍では変化が少なく、赤や紫の領域で顕著なシフトが観測されるのは、こうした視覚受容野の特性によるものである。
色空間設計における幾何学的歪み
色彩工学の視点から見ると、アブニー効果はCIE色度図などの色空間における「等色相線」が直線ではなく、曲線を描くという事実として現れる。これは、色空間上の白色点とある色を結んだ直線上を移動しても、知覚的な色相は一定に保たれないことを意味する。
ディスプレイや印刷のカラーマネジメントにおいて、特定の色を淡くしていくグラデーションを作成する際、意図せず色味が転んで見える現象は、多くの場合この効果によるものである。計算上の最短距離(直線)と、人間の知覚上の等色相(曲線)が一致しないため、単純な補間計算では視覚的な違和感が生じる。
広色域時代のカラーアピアランスモデル
近年、HDR(ハイダイナミックレンジ)や広色域ディスプレイ(BT.2020など)の普及に伴い、アブニー効果の影響は以前にも増して大きくなっている。高彩度領域から無彩色領域までのダイナミックな変化を表現する際、従来の色空間モデルでは視覚的な歪みが顕著になるからである。
最新のカラーアピアランスモデル(CIECAM02やCAM16など)の研究においては、この非線形性を数理的にモデル化し、補正項として組み込むことが標準的となっている。物理的な発光特性と人間の主観的な見え方のギャップを埋めるためには、アブニー効果のような生理学的な視覚特性を厳密に計算式へ落とし込む作業が求められる。
最終更新日:
