脱皮する
脱皮することの出来ない蛇は破滅する。その意見を変えることが妨げられた精神の持ち主たちも同様である。彼らは精神であることを止める。 曙光 573 「脱皮する」ということで、人の成長について書いていきます。 十代の頃は、小学生から中学生、その先は人によりますが、高校生や大学生などになったり、働きだしたりと、その度に何となく違った世界が広がっていって成長しているような感じになります。 人間で言う脱皮という表現に当てはまるのが、世界の見え方です
真理とは何か?
神がまさしく真理でないとしたら、そしてまさしくこのことが証明されたとしたら、どうだろう?神が人間の虚栄心であり、権力欲であり、短気であり、恐怖であり、喜びと驚きの妄想であるとしたら、どうだろう? 曙光 93 後半 「真理とは何か?」 といきなり胡散臭いカルトのようなタイトルですが、特別企画なので仕方ありません。 カルトもよく真理という言葉を使いますが、「教祖に財産をお布施しないと地獄に落ちる」等々、それは真理ではありません。 しかしなが
最初に病が治った思い出の地へ
最初に病が治った思い出の地へということで、近々約10年ぶりに奈良県吉野郡天川村に行くことを予定しています(来週に行きます)。 行ってきました⇒「大峯山(大峰山・山上ヶ岳)2017」 いつも涙とともに何か大きな気付きをする時は、桜井市の長谷寺だったり、今回の予定地である天川村の大峯山だったりと、なんだか奈良県が多い気がします。 と言っても、今回お伝えする第一の覚醒のような事が起こった時は、天川村ながら時間の関係上大峯山(大峰山)こと山上ヶ
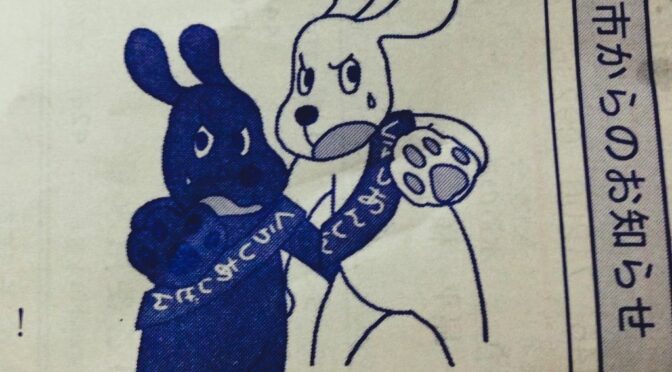
われわれは人生に安心を望む
思索家のように、通常は思想と感情との大きな流れの中で生き、夜の夢すらもこの流れを下って行くのなら、われわれは人生に安心と静けさとを望んでいるのである。― 他の人々は、彼らが省察に身を任せるとき、まさに人生から離れて休息したいと思っているのに。 曙光 572 安心と安全こそが、人生の最大のテーマであったりします。安心とはもちろん不安がない状態のことを意味します。 普通はそれを思考上で解決しようとしますが、思考上で考える安心や安全は、本当の
党派の中の勇気
あわれな羊たちはその隊長に言う。「とにかく先に立って行ってくれ。そうすればわれわれは君について行く勇気を決して無くさないであろう。」あわれな隊長はしかし心の中で考える。「とにかく私の後をついて来てくれ。そうすれば私は諸君を導く勇気を決して無くさないであろう。」 曙光 419 「会社組織の中で」などなど、ある組織の内側にいる間は、その組織の内側で勇気を振り絞り、様々な知恵を巡らせ、何とかその組織を変えようとしたりすることがあります。 概ね
魂の野戦薬局
一番の特効薬はどれか?― 勝利だ。 曙光 571 一番の特効薬はどれか?― 勝利だ。と、すごくシンプルでわかりやすいですね。 あれこれうじうじ言っていた人も、勝利のようなことが起こるとそれまでの陰鬱が全て吹き飛んで、周りを辟易させていたことなどすぐに忘れたりします。 「勝利」により陰鬱が全て吹き飛ぶ 借金体質の人の勝利、それはお金を借りれた瞬間です。 フラれた人の勝利、それは新しい出会いです。 就活難民の勝利、それは内定です。 そのよう
損失
悲嘆を抑制し、ちょうど高く暗い糸杉の下のように沈黙して歩む崇高さを、魂に分かち与える損失が多々ある。 曙光 570 損失ということで、人生の無駄についてでも書いていきましょう。 世の中にはたくさんの無駄があります。結果的にそんな無駄な経験があとになって良い経験として解釈されることもありますが、特に大人になってからの無駄な経験は身を滅ぼすようなものがたくさんあります。 そしてそれが無駄だということを頭ではわかっていてもやめられないというこ
悲惨に耳をふさぐ
他の人たちの悲惨と苦しみのためにわれわれが陰鬱な気持ちになり、われわれ自身の空を雲で覆うのなら、だれが一体この陰鬱の結果を引き受けなければならないのか?まさしくやはり他の人たちである。 曙光 144 序 ある感情が起こった時、その感情を自らが受け入れぬまま人と会うことによって「感情から目をそらす」ということをよくやっている人がいます。 人の暗い話を聞くと、聞いた側までも暗くなってしまいます。ということは、いつも周りにグチグチ言っているよ
健康保護のために
犯罪者の生理学を考察し始めるや否や、犯罪者と精神病者の間には本質的な区別がない、という避けがたい洞察の前にすでに立つことになる。 曙光 202 序 思考によって生じた嫌な感情、抑圧されたエネルギーが吐出口を求める時、その人の気質が外向的であれば暴力的に、犯罪の方に走り、内向的であれば自傷行為に走る傾向にあります。 そう考えると、犯罪者も精神病患者も元のエネルギーの質としては同じようなものを抱えているという感じになります。 うつ病などにし
あらゆる謙遜の限界
不合理なるがゆえに私は信じると語り、その理性を犠牲に供するような謙遜は、おそらくすでに多くの者がなしとげたであろう。しかし私が知るかぎり、それからともかく一歩だけ離れていて、私が不合理なるがゆえに私は信じると語る、あの謙遜をなしとげた者はいない。 曙光 417 あらゆる謙遜(けんそん)の限界ということで、謙ることについてでも触れていきましょう。 慇懃無礼(いんぎんぶれい)という言葉があるように必要以上の謙りは一種の皮肉となり、時に相手に
貴族の将来
高貴な人々の挙動は、彼らの身体の中で、絶えず力の意識が魅力的な演劇を演じていることの表現である。そこで、貴族的な風習の人間は、男性であれ女性であれ、さも疲れたようにして椅子に腰を下ろすことが嫌いである。 曙光 201 序 先日の投稿「貧困に耐える」で触れた貧乏マインドの反対にあるのがこうした貴族的な風習です。「さも疲れたようにして椅子に腰を下ろすことが嫌い」という感じです。 まあまた新約聖書マタイ6章的ですね。引用しておきましょう。 断
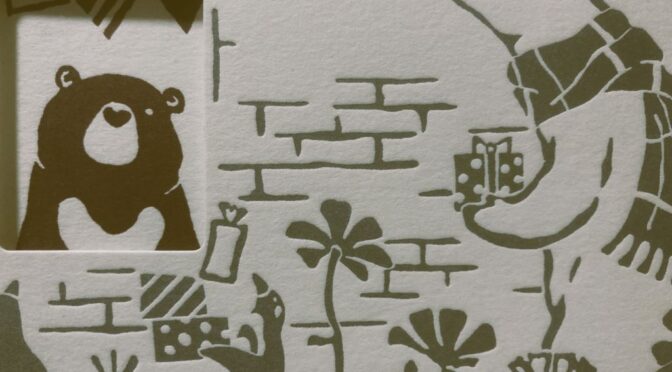
愛の治療法
相変わらず大ていの場合愛にはあの古い荒療治が効く。愛し返すことである。 曙光 415 愛の治療法ということで、冷めた男女の治療法についてでも書いていきましょう。 冷めた男女の治療法を求め、冷めた関係の修復や復縁を切に願っているというケースもよく見られますが、たいていはその執着によって関係修復や復縁とは逆行した流れになることがよくあります。 「前と同じとまではいかないが、そこそこ愛し合えるような関係に戻れたらなぁ」 そうは思いつつも苛立ち
貧困に耐える
貴族の素姓の大きな美点は、その素姓が貧困をよりよく耐えさせることである。 曙光 200 貧困と貧乏マインドは相関関係どころか因果関係ですらあります。 寄付をすると金持ちになる、というようなことが囁かれる場合がありますが、問題はその行動ではなく、その行動時のマインドにあります。 実際の行為行動よりもその時の精神状態の方が重要です。 貧乏マインド その理屈は非常に簡単で、貧乏マインドなら「惜しい」と思い、「数限りあるお金が減っていく」という
この衝動が荒れ狂いさえすれば、禍いなるかな!
他人たちに対する愛着と配慮の衝動(「同情的好意」)が現在の二倍の強さになるとすれば、地上では全く耐えきれないであろう。日々刻々、各人が自分自身に対する愛着と配慮からどんなに数々の愚行を犯すか、またそのとき彼がいかに耐えがたいものとみられるかを、まあちょっと考慮するがよい。 曙光 143 前半 人に止められてでもやってしまうこと、それが良い方向に動けば偉業が成し遂げられ、悪い方向に向かえば我が身を滅ぼすことになりかねません。 悪い方向に向
共感
他人を理解するために、すなわち、彼の感情をわれわれの内面で模像するために、われわれは実際しばしば、彼のしかじかの一定の感情の起因を尋ねて、たとえば、なぜ彼は悲しんでいるのか?と問う。― そうすると同じ起因にもとづいて自分でも悲しくなる。しかしそれよりもはるかに普通であるのは、そうしないで、感情が他人において及ぼしたり示したりする結果に従って、その感情をわれわれの内に引き起こすことである。 曙光 142 「他人に共感する」ということがよく
われわれの方が高貴である
忠実と、寛容と、名声への羞恥心。この三つがひとつの心情に合一すると― われわれはそれを、貴族的、高貴、高潔と呼び、これによってギリシア人を凌ぐ。 曙光 199 序 「高貴」という字を見ると、どうしても10代の頃にオールディーズライブハウスで見かけた「軽快にステップを踏む髭のおっさん」を思い出してしまいます。 「こうしたものの嗜みもあるぞ」という感じで得意げです。高そうなスーツに口髭、「ステキですね」の一言を欲して仕方ないという感じでしょ
倫理的な奇蹟
倫理学という科目がありますが、何だか哲学とごっちゃにされていたりしつつ、「誰々の〇〇という思想はどういうものか?」というお勉強の類に終わっているのが非常に残念だと思っています。大学の学部に関しても、海外では哲学部というものが結構あるそうですが、日本では文学部哲学科という省庁で言うところの庁くらいの位置付けになっているようです。 義務教育ではそうした哲学や倫理思想、そして道徳がごっちゃになっていて、ありえないほどの短絡的な道徳が教え込まれ
序列をその国民に与える
多くの偉大な内面的な経験を持ち、精神的な眼でそれを見つめ、見渡すこと― これが文化人たちを作り出す。彼らがその国民に序列を与えるのである。フランスとイタリアでは、貴族がこれを行なった。貴族がこれまで一般に精神の貧困者に属していた(おそらくもはや長いことではあるまいが)ドイツでは、司祭や、教師や、彼らの子孫がこれを行なった。 曙光 198 少し昔までの日本では、「わかりやすい普通」が作られていました。エコノミックアニマルと呼ばれたりして、
威厳と無知の同盟
そうだ、われわれの無知と、知識に対するわれわれの渇望の乏しさとは、威厳として、性格として、肩で風を切って歩くことを見事に心得ている。 曙光 565 文末 威厳を欲することはありませんが、社会の中で過ごす場合は、威厳がモノをいう時があります。それは蔓延する体育会系思想、儒教思想的なものの影響が大きいでしょう。こうした威厳のような権威性は、儒教思想下にある場所以外でもどこの地域でもあるようなことですが、 「威厳がある方が何かとやりやすい」
より美しいが、価値は劣る
絵のように美しい道徳。それは、まっすぐにほとばしりでる感動の道徳であり、けわしい通路の道徳であり、激昂した、強烈な、ものすごい、荘厳な挙動と口調の道徳である。それは道徳の未開の段階である。その美的な刺戟によってそそのかされて、高級な順位をそれに割り当ててはならない。 曙光 141 より美しいが、価値は劣るということで、安物の心理学を駆使する水商売の人や胡散臭い人、そうした人たちに騙されてしまう正体である「劣等感」についてでも書いていきま
不足の中にある精巧さ
ギリシア人の神話が諸君の深遠な形而上学に匹敵しないからといって、軽蔑してはならない!その鋭い知性にまさにここで停止を命じ、スコラ哲学や、理屈をこねる迷信の危険を回避する如才なさを十分長い間所有した民族を、諸君は驚嘆すべきであろう! 曙光 85 世を見渡してみると、「結局何がしたいんだ?どうありたんだ?」としか思えないような構造がよくあります。 何となく世間では良しとされている中間ゴールのようなものを盲目的に目標として、こなした先にあるの
「うつ」を自力で克服する
「うつ」を自力で克服するということという感じで、根本的なことについて少し書いていきます。いわば「治るときはすぐに治ります」の純粋な続編ですね。 「うつ、もしくはうつ気味の方へ」というカテゴリの中の投稿数はそれほど多くありませんが、一応毎度毎度いつもよりは力を込めて書いていたりします。なぜ今まで書かなかったのは自分でも不思議ですが、どうしてこんなテーマを取り扱うことにしたのか、という点をもう少し仔細に書いておきます。 もちろんこのブログは
キリスト教の文献学
キリスト教が誠実と正義とに対する感覚を陶冶することがいかに少ないかということは、キリスト教の学者たちの著作の性格の上からかなりよく見積もることができる。彼らはその憶測するところを、あつかましく、あたかも教義のように提出し、聖書の章句の解釈に関して誠実に困惑することは、稀である。 曙光 84 序 あまりストレートに宗教学的な分野に触れるつもりはありませんが、どうしても曙光の中にはキリスト教を名指しして書いている箇所が多くあります。今回も「

洗脳系自己啓発コンサルタントの実態
洗脳系自己啓発コンサルタントの実態ということで、カルト並みに洗脳された自己啓発コンサルタントに会ったので、書き記しておきます。 以前、胡散臭いコンサルの次はポンコツなコンサルで、胡散臭い経営コンサルタントやポンコツなコンサルタントについて書きましたが、今回はカルト宗教並の洗脳状態を目の当たりにしたので、自己啓発への警鈴という「自己啓発」コーナーを設けようと思ったしだいです。 自己啓発やコーチングのようなもの自体を全て否定するわけではあり
被虐と解放
「男と女」タグ創設記念として、被虐と解放というものを中心にモテテーマでも書いていこうと思います。被虐とは、もちろん虐げられること、虐げを受けることを意味しますが、そうした被虐に対する無意識の欲求を解放するというような感じです。 いきなり怪しそうな被虐と解放というタイトルにしましたが、声を大にして言っておきたいことがあるのでストレートなタイトルにしました。 それは非常に単純で、勘違いサービス、つまり本質からズレたような加虐者もどきがあまり
間や空白に対する恐怖と勇気
間や空白に対する恐怖と勇気というような感じで、「間」や「空白」に対して意識的・無意識的に持っている恐怖とそれに対する勇気のようなものについて書いてみます。 ちなみに「間」は「ま」でも「あいだ」でもどちらでもよく、そうしたものを包括していると考えてもらうほうがわかりやすいかもしれません。 音楽でもある程度技量が上がってくると「休符を聴かせる」という領域になりますし、文学でも行間を作ることが表現としての幅を広げていきます。笑いにおいても「間
道徳教師の虚栄心
道徳教師が全体として成功することが少ないのは、彼らがあまりにも多くのものを同時に望んだこと、すなわち、野心に燃えすぎていたことで説明される。彼らはあまりにも快く、万人に対する処方箋を与えようとした。 曙光 194 序 万人がこぞって理解できるような道徳というものはなかなかありません。道徳が倫理的なものであり、社会の中の関係性を示すようなものだからというのがその最たる理由でしょう。 ともすれば、全体に適用するのか個に適用するのかというよう
エスプリと道徳
精神や、知識や、心情を備えていながら退屈であるという秘密に通じ、退屈を道徳的なものと感じることに馴れているドイツ人は、― フランスのエスプリに対して、それは道徳の眼をえぐり抜きはしないか、という不安を抱く。 曙光 193 エスプリ(esprit)は精神というような意味ですが、フランス語のためフランス的な精神という感じで使われます。まあ日本で言う「大和魂」「島国根性」といった感じで捉えても問題ないでしょう。 フランスについてもフランス語に
人生をリセットする
よく「人生をリセットしたい」とか「リセットボタンがあったらなぁ」なんてなことを言う人がいますが、まあとりあえずは現状が嫌で仕方がないのでしょう。 そういうわけで、うつテーマとして「人生をリセットする」といったことについてでも書いていきます。 「人生にリセットボタンなんて無いぜ」みたいなことを言う人もいますが、おそらく巻き戻して同じ人生の延長で「あのシーンを修正したい」ということに対してにでも言っているのでしょう。 記憶の連続性と人生のリ
小心者
ほかならぬ不器用で小心な人たちこそ殺害者になりやすい。彼らは目的にかなった小さな防御なり復讐なりの心得がない。精神と沈着な心構えとの欠乏のため、彼らの憎悪は絶滅以外の打開策を知らぬ。 曙光 410 なんだか曙光のこの項目を見ると北九州一家監禁殺人事件の緒方純子受刑囚を思い出します。それだけでなく、世のDV被害者が浮かびます。変な宗教まがいの団体に洗脳された人たち、パートナーに洗脳されてしまった人たちがどうしても思い浮かびます。 小心者と
