選択と制限と生成と発展
イエス・キリストの意志を「キリスト教」が踏み潰したということをニーチェが示すように、ある体系だった合理性や組織、マニュアルこそが、生命の意図するところを阻害していきます。 AはBであるべきであり、Bであれば満足するという構造が苦を生むということにもなりますが、ここで生じるのは、AがBではなくCであるということを受け入れることも苦を生じさせるという点です。 ― 純化させるということは、とどのつまり、それのみを選ぶということではなく、一切の
本格的な哲学空間の前に
ある程度、精神の状態が変化しつつあっても、数回寝て覚めればまた元通りになるのは、体に張り巡らされた神経的な基準に引き戻されているから、ということで、本格的な哲学空間に向かう前に、この体の基準を徹底的に変更していくとよいのではないか、と思うことがあります。 ある日、あることに納得してあることを決めたとしても、数日、数週間経てば、なぜかその納得に納得しなくなるというような現象があります。 これは結局、体が慣れ親しんだパターンに引き戻されると

結局は気持ちひとつ
何をしている時よりもニーチェ等々を再読している時の方が「頭がスッキリする」という一種の異常性を持った僕は、とどのつまり、世に溢れている情報のレベルなど全く刺激にすらならない、というような程度にある意味で高耐性なのだろう言うことを思ったりします。 色々な人が色々なことを言いますが、何となく前提が違うというようなことをいつも思ったりします。 そういう時にニーチェくらいの方が感覚的にスッキリしたりします。 それは例えば、何かしらの理屈を説かれ
変化・期待的意図
人の気持ちというものは変化の度合いによって幸福感のようなものを感じるようにできています。 なので、意図としてマイナスからゼロへという変化とそれに対する期待で楽しんでいるフシがあります。 自我によるやみつきゲームのようなものです。 こうなりたいと思いつつも、実は気持ちの奥底ではそうなってほしくないと思っていたりするわけです。いつものパターン(マイナスからゼロの安らぎ+期待)や本質的に求めているものと遠ざかってしまうためです。 知人の士業の

超人的感覚の意図するところ
論理的整合性は意図的に無視して「誰にでも読めて誰にも読めないかもしれない」という感じで、超人的感覚について触れていこうと思います。 最近、特に自分が意識していなくても、ニーチェやエリクソンやゼランドなどが僕の世界に入っていきます。なので、そうしたテーマに沿って書いていこうと思います。 怒りにしても欲にしても、何かしらのソワソワ、緊張をなんとかしようというようなものが根底にあります。 生きていて一番厄介なのは「正論っぽいこと」です。正しそ

変性意識と情報処理能力の限界
変性意識というのは、現実世界への臨場感よりも別の仮想空間への臨場感が強い状態なので、厳密に言うと常に変性意識状態です。ただ、ここでは深い変性意識状態、いわゆるトランス状態について触れていこうと思います。 そして、そうしたものと近年の情報処理能力の限界を超えた人たちについても触れていきます。 一応補足資料としては新規謎コーナー「AIとの対話」に置いてあります。 AIが人間に与える意識変容(変性意識) 本当の脱変性意識状態は、阿羅漢しかたど

情報を揉む
情報を揉むというようなことについてでも触れていこうと思います。 この情報というのは、情報空間であり情報宇宙のようなものです。ちょっとややこしいですが、バイト表現されるような情報とは少し違います。 思いっきり哲学テーマを書こうと思う時もあるのですが、まとまった時間とそこそこの体力が残っていないと中途半端になるのでしばらくは出せずじまいです。 ただ、何となくちょっとだけ触れていこうと思います。 意識の向きを調整する 「意識の向き」というもの

捨て身と自己愛の矛盾
捨て身と自己愛の矛盾とその先にあるものについて触れていこうと思います。 「思い切り」というものは、その最高地点が玉砕のような捨て身でありつつ、なぜそれを選択しているのかという点で因を観察すると深い部分で自己愛があります。 これは同レベルで照らし合わせると矛盾になりそうなところです。 カルマ、悪業云々を根拠に苦行をするというのは、まさにこうした捨て身と自己愛の矛盾がふんだんに含まれています。 苦行によってどうなりたいのかと言えば自己愛に基

情報を触ることと散らかりをまとめること
6月の半ばくらいから僕は本格的に毎日機嫌の良い毎日を過ごしています。 しかしながら、暑さのせいもあるのか周りの機嫌が良くないときがあります。 「知らん」といえばそれまでですが、機嫌が悪い人をよくよく観察してみると、単に意識が散らかっているだけではないかと思ったりもします。 最近特に実感しているのが、傲りでも何でも無く8割以上の人たちにおいて「びっくりするほど頭が良くない」ということです。厳密には頭が回っていないという感じです。別の側面か

情報のかたまりとの付き合い
情報のかたまりとの付き合いについて触れていきます。 結局意識の向きだけで経験することは決まっていきます。 経験に思考も感情も関係はありません。 ある情報のかたまりに意識の向きを向けると、比喩的に表現すればエネルギーを吸い取られます。 そして、その情報のかたまりは何もしてくれません。 それそのものの意志の方向があるだけです。 たまに同調していると、嬉しさや楽しさを経験させてくれることがあります。 しかしそれに飲み込まれてはいけません。 夜

思考によるあらゆる緊張と現象の展開
本来、安らぎが当然であり、結局、緊張がなければ安らぎが表に出てきます。 無駄な緊張というものは、思考により生じます。四苦八苦のほとんどは、これら思考による苦しみを示しています。そして突き詰めればすべてがこういった思考や意識による苦しみです。 これはすべてが苦しみであるという消極的なことを示すばかりではなく、苦を示すことで安らぎを示すものとなります。 イメージとしては、何かの形を線で描かなくても、それ以外の背景を塗りつぶしていけば、何かの

狂人たちの中にいて狂人にならずにいること
狂人たちの中にいると、狂っていないはずの自分がおかしな存在として扱われ、彼らと同じような狂人にならないと不快感が生じてしまうというような同調圧力がかかることがあります。 古くは中学生時代の体育会系的な圧力、その後も脳筋要素が強かった勤め人時代の職場もそんな感じでした。 最近では、介護関連でよく狂人に出くわしました。 狂人は狂人であることを認めません。 狂人から見れば僕の方こそ狂人に映ります。 相手から見て狂人である僕を何とかしようとして

吠えたける悪魔の取り扱い説明書
「吠えたける悪魔」はどこにいるかというと、結局は自分の内側にいます。 その構造を分解して考えればすぐに見破ることができます。 例えば、僕が父の中にいる「吠えたける悪魔」を浴びて何かしらの嫌な思いをしたとすれば、その嫌な思いという情報、「父をはじめとした家族との関係性において生じた何かしらのもの」がその本体になるわけです。 人を通じてやってきたからと言って、その人自身が悪魔であるわけではありません。そしてその「悪しき情報」や現象を呼び起こ

デコピンで終わり
強くなるということは、大きくなるということです。 大きくなるということは、囚われないということです。 ー 時に、「どっちの選択が囚われないということなのだろう?」という難題がやってきます。 「どっちの選択をすることが『囚われていない』ということになるのだろう?」 というような感じですね。 そんな時は、「どっちの選択をすることが『囚われていない』ということになるのだろう?」ということに囚われないことです。 そうするには少しコツがあります。

他人の都合と抵抗
他人の都合というものは厄介なものです。 何が厄介かと言うと、時に「自分を尊重する」というものと「相手を尊重する」というものがぶつかるからです。 抽象化して統合された都合を発見できればいいのですが、相手が狂っていたりすると、相手の都合ばかりが迫ってきたりします。 そうした感じで迫られた時に、「相手の都合や状況も理解できるからなぁ」と思って関わるとロクなことが起こらないという場合があります。 手をかけようと思って手をかけること自体が、相手を

吠えたける悪魔との戦い
今に始まったことではありませんが、なぜか僕には吠えたける悪魔が常に挑んできます。 その吠えたける悪魔との戦いを何十年も繰り返しています。 おそらく元々は、父の中にある「劣等コンプレックス」や「愛着障害や承認欲求」のようなものです。そこに「社会的洗脳」というものが絡み、エネルギーの逃げ道を塞いでいます。 そのイメージが直接間接を問わず僕に挑んできます。 ちなみに聖書中の「サタン」とは、「道を塞ぐもの」「邪魔をするもの」というような意味があ

知識の習得という逃避と内なるものへの実践
実践という言葉自体が、知識を用いて自然や社会に対して行う実際の行動、つまり知識を組み立てて形成した主義や思想を元に外界に働きかけること等々として定義されている感がありますが、そうした事を言っている人たちは、なんだか偉そうなことを言っているように見えて、単に逃げているだけであると考えることもできます。 厳密には逃げていると言うよりも「自らの思考に騙されている」といった方が正しいのかもしれません。 世の中にはたくさんの知識のようなものがあり
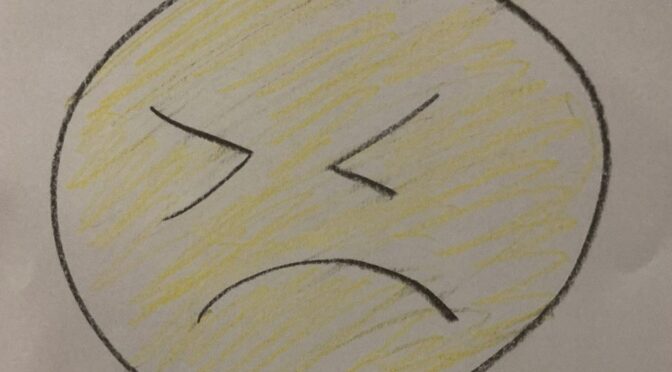
人の尊厳と可能性
本投稿で「雑記」400投稿目となりました。ということで、「人の尊厳と可能性」についてより身近に、そしてより深く雑記らしい雑記を書いていこうと思います。 最近「プロ意識が欠如している」というか、「もうちょっとしっかりしろよ」という人によく出くわします。 まあ職業というものをどういうふうに捉えているのかによりますが、たいてい「お金のため」とか「親に半ば強制されて」等々嫌々その仕事をしているという人ほどプロ意識が欠けています。 患者のことなど

浦島太郎感からの脱却
ここ数年の僕は、まさに浦島太郎でした。ある程度頭が元に戻ってきた時、社会を見渡すと、「どこだここは?」というような気分になっていました。 コロナ環境やコロナ罹患、そして娘との生活とそれによる睡眠不足、母の脳出血等々、様々な要因によって頭が破壊され、一時的に世界の把握ができなくなりました。一度地に落ちたようなものです。その一部は「感染後の集中の乱れ」で触れていました。 しかしながら、そんな浦島太郎感もなくなりました。さらにいうと以前よりも

情報の破壊
気力や体力がない時、「治そう、回復させよう」と考えます。それでうまくいくときもありますが、うまくいかないときもあります。 それはマイナス要因が大きすぎる時です。 このマイナス要因というのは何かということを突き詰めると、意図の障害になっている情報状態です。 また、治しても治しても復活する体のこわばりや痛みがある時、特定の情報による慢性的な緊張や炎症が潜んでいる場合があります。 なので表面的に治療しても、また緊張によって復活します。 何かし
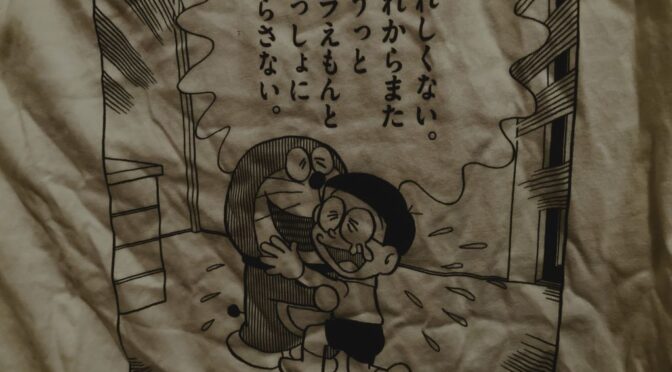
ドラえもん的視点
ふとドラえもん誕生の時の藤子・F・不二雄氏を思い出したのですが、その誕生の時の発想やマンガ自体が「現代の哲学がようやく追いついてきている視点」であることに気づきました。 大きく分けると ドラえもん誕生の時のF先生の思考 「タイムマシンがあったら未来の自分からアイデアをもらってくるのに」 という点、そして 「ドラえもんの世界自体がパラレルワールドであるということ」です。 前者はやや大乗仏教的です。 後者は「量子的な重なり合いの解釈」として

現実を無視する
「なんとかなる」の続編です。 それは「現実を無視する」です。 「現実が変わらないのであれば困る」ということになりますが、その意見は自我の意見です。現実を変えるために「なんとかなる」と思い込もうとして、安心したフリをするというのは誤りです。 「なんとかなる」と心底思って安心して意識の向きが明るくなったのに、現実を確認してまた騒ぐということを繰り返してはいけません。 なので、より厳密に言えば、「なんとかなる」の状態になったら、不安・恐怖を伴

思考や感情と私
思考や感情というものは、ただの反応にしかすぎません。 ただの反応にしかすぎないものを、あれこれこねくり回そうとすると、また反応が起こるだけという感じになります。 しかしながら、ひとまず暗い思考のループなり、不快な感情なりを「何とかしたい」と思っているからこそ、それを弄くり回そうとするという構造は理解することができます。 反応をしないでおこうとしても、結局反応をしていないフリをするのがオチです。 本質的には、「どうするんだ?」という問いに
既にあるものと心
無限にある既に形成された状態、そうした混沌と心について触れていきましょう。もちろん、ここで触れることは通常の思考では意味不明のように見える可能性もあります。そして、あえて証明の証明のようなことはパスしていきます。 まずこの空間は、いまただ単にあるものがあるという状態です。 それはこの瞬間に確定しています。同時に、時間というものもあくまで自我が「再生」の如く捉えているだけになります。 この心はただの認識する働きです。受け取るだけです。 ど

困難を乗り越えることについて
「困難を乗り越えること」についてでも触れていきましょう。いきなりですが、困難は、困難を欲した時にしか生じません。「何かしらの困難を乗り越えることで、何かを叶えたい」というものであっても、「こんな困難はコリゴリだ」という場合でも、いずれにしても、それらは「作り上げれたもの」にしか過ぎません。 困難というものは、それを支える「因」と「縁」が無いと生じません。ということで、困難というものも、「今、形成されているもの」です。 この因縁は、世間一

木漏れ陽が灼く影
この8月、なぜか昔お付き合いしていた方に二人も会いました。共に「ばったり」です。今でもキレイでしたね。でも、それぞれの方に特に思い入れはありません。 思い入れは無いのですが、やはりそれら方々に共通して「なんで?」という疑問がありました。 なぜか「ふっ」と気分が変わるんですね。 気持ちの上で何が変化するのかということがわかりませんし、分かる必要もないと思っています。 何かが足りないというわけでもないのでしょう。 何かが嫌だというわけでもな

「思い込みを外す」ということ
「思い込みを外す」ということについてでも触れていきましょう。世の中ではいたるところで「思い込みを外しましょう」ということが言われたりします。経営論を始め、メンタルケア的な分野、人生論的なところまで様々なところで、思い込みを外すというような点について語られています。 ただ、「思い込みを外す」ということについて、世間的な目線で近視眼的に捉えてしまうと、本当の意味での「思い込みを外すこと」は難しくなってしまいます。 無理をしたり、抑え込んだり
祝九周年
本ブログも九周年を迎えることになりました。ちなみにこれで2119記事目になります。今回は、単純に九周年というタイトルです。 祝八周年の時は2022記事だったので、この一年で100弱の投稿をしたことになります。 さて、常連さんいつもご高覧ありがとうございます。コメントを寄せていただいた方やcontactからご連絡を頂いた方、また、ひっそりと読んでいただいている方々、いつもありがとうございます。 アクセス状況 この一年でこのブログにやってき
第2100回投稿記念
これで2100記事目になります。ブログ創設から2100回目の投稿ということで「第2100回投稿記念」です。 前回の第2000回投稿記念は、2021年12月27日だったので、前回からの100記事は、1年と少しかけて投稿したという感じです。またローペースで、かつ、アフォリズムで少し数を稼いだ感はあります。 さて、常連さんいつもご高覧ありがとうございます。 また、contactからご連絡いただいた方、投稿にコメントをいただいた方、ありがとうご
暇つぶしと集中力の分散による怒り
11月は児童虐待防止推進月間ということで、今年も少しだけ児童虐待防止について触れていきましょう(なお、昨年の「しないこと」への評価で触れていますが、個人的には言葉的には児童虐待防止よりも児童愛護の方が表現としては良いのではないかと思ったりします)。 根本的にこうした虐待については、怒りが根底にあります。倫理上虐待というものは、それほど論証を必要とすることなく否定されるようなものであり、している本人たちもたいていそれを頭で理解していること
