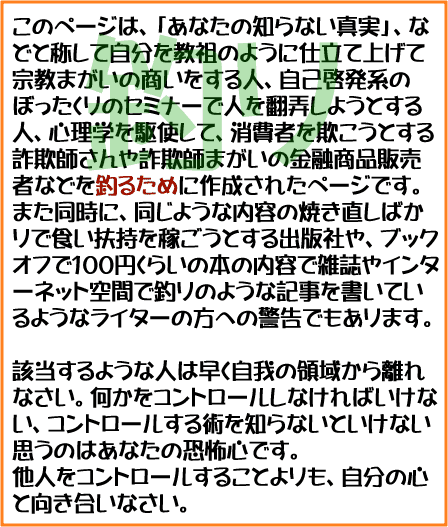
アンビバレンス効果(ambivalence)とは、両面価値や両価感情と訳され、同一の対象に対して、相反する感情や態度を同時にもつ現象およびその現象による心理効果のこと。相反する感情を同時に起こったり、相反する態度を同時に示すことがアンビバレンスである。なお、ドイツ語の「ambivalenz」から「アンビバレンツ」とも呼ばれる。こうした相反する両面の感情が同時に起こった時、どちらか一方の感情が抑圧され、抑圧されたものが行動に影響を与えるというのがアンビバレンス効果(アンビバレンツ効果)である。
目の前の現象自体は無属性だが、それに対する価値判断をなしたり、その現象が発端となって感情が起こる。そうして現象を捉えた時の印象は、単に一つの種類のものだけでなく、相反する感情が同時に起こったりする。
両面価値・両価感情 評価や感情の相反
様々な異なる視点から複数の評価を下すこともできるので、現象への評価や感情が相反したり、かなり複雑に絡み合うこともしばしばある。こうしたことをアンビバレンス(アンビバレンツ)と呼び、その時に起こる抑圧現象およびその抑圧が行動に影響を与えることをアンビバレンス効果(アンビバレンツ効果)と呼ぶ。
端的にアンビバレンス(アンビバレンツ)とは「好き」と「嫌い」といった二元論的で両極端な印象であり、それが同時に起こった時にどちらかを封印してしまう。そうして封印してしまった感情が行動に影響を及ぼすのがアンビバレンス効果(アンビバレンツ効果)である。
相反する感情の一方が無意識下に抑圧される
通常、両価感情が起こると一方の面(多くのケースで望ましくない面)が無意識下に抑圧され、その人の行動に影響を与えるとされる。
アンビバレンス(アンビバレンツ)の例としては、「尊敬と軽蔑」や「愛と憎しみ」などの感情を同時に持つことであり、この言葉はスイスの精神科医オイゲン・ブロイラー(Eugen Bleuler)が使用し、後にフロイトが精神分析理論に組み入れた(「美しさと醜さを同時に感じる」といったケースもあるだろう)。こうした両面価値、両価感情が昂じると葛藤状態に陥り神経症や精神分裂病の原因となるとフロイトは考えた。
「目の前に提示された商品は素晴らしいと感じたが、店員が鬱陶しく、そんな鬱陶しい店員を雇う業者は胡散臭い」という場合でもアンビバレンス(アンビバレンツ)が起こる。
勤めている会社やその製品・サービス、そして同僚のことは好きだが、上司のことは大嫌いであるといった場合もアンビバレンス(アンビバレンツ)が起こる。
会社に行くか行かないかという行動の選択において、生活費を稼ぐためという面も影響を与えているが「そのオフィスという空間に入りたいか入りたくないか」という面で考えると「同僚とは会いたい」という面と「嫌な上司には会いたくない」という面が相反して起こる。
結局オフィスには入るのだが、その時「仕事はしなくてはならないし、同僚にも会いたいから」ということが際立ってその行動を起こしたことになるが、「上司のことは大嫌いで顔も見たくない」というネガティブな感情は消えたわけではない。
この時もアンビバレンス(アンビバレンツ)が起こっている。
アンビバレンス効果(アンビバレンツ効果)は、相反する感情の一方が無意識下に抑圧されることで行動に影響を与えるということになるので、水面下では「意識がどんどん蝕まれている」ということになる。そして限界を超えると精神疾患になるということを考えたというのがフロイト(Sigmund Freud)的な理解である。「両面価値、両価感情が昂じると葛藤状態に陥り神経症や精神分裂病の原因となる」という部分である。
なお、フロイトに従って精神分裂病と表現したが、現在では統合失調症と表現されている。これは「精神が分裂する」という視点から、「統合することがうまくできない」という視点へと捉えられ方が変化したことによる。「常にまとまり」があるという視点から「常にバラバラのものを毎度まとめている」という視点に変わったということがその理由である。
葛藤や抑圧の解放
両面価値、両価感情が昂じると葛藤状態に陥り、相反する感情の一方が無意識下に抑圧され、神経症や精神分裂病の原因となるのであれば、そうした葛藤状態や抑圧されたものを発見し、解放することによって症状が収まるという風に考えることもできる(自分を制限しているものを観て限りなく壊せ)。
また、人が笑う要素として、このアンビバレンス(アンビバレンツ)によって抑圧された部分が解放されることで笑いが生じるという部分がある(ある人にとっての「面白い」が、ある人にとっては「面白くない」のは、なぜなのか)。
両価的葛藤の力学と意思決定における機能的役割
アンビバレンス(両価性)とは、単なる「迷い」や「優柔不断」と同義ではない。それは同一の対象に対して、相反する感情や評価が同時に、かつ高い強度で共存している心理状態を指す。愛着と憎悪、魅力と嫌悪が拮抗するこの状態は、心理的な緊張(テンション)が高まっていることを意味し、静的な無関心とは対極にある動的なエネルギーを内包している。マーケティングや対人影響の文脈において、この不安定な均衡状態を理解することは、相手の態度変容を促すためのレバレッジポイントを見極めることに他ならない。
精神分析から社会心理学への概念拡張
この概念は、1910年に精神科医オイゲン・ブロイラー氏によって、統合失調症の基本症状として提唱されたことに始まる。彼は、患者が同一の人物に対して「愛」と「憎しみ」を同時に抱く分裂した精神状態を記述するためにこの語を用いた。ジークムント・フロイト氏もまた、エディプス・コンプレックスにおける父親への敵意と敬愛の共存など、精神発達の重要な局面においてアンビバレンスが本質的な役割を果たすと考えた。
その後、この概念は臨床の場を離れ、社会心理学における「態度(Attitude)」の研究へと拡張された。かつて態度は「好き―嫌い」という単一の直線(一次元モデル)上で測定されるものと考えられていたが、カシオポらの研究により、ポジティブな評価とネガティブな評価はそれぞれ独立した次元(二次元モデル)で処理されることが明らかになった。つまり、人間は対象に対して「肯定も否定もしない(無関心)」状態と、「強く肯定し、かつ強く否定する(アンビバレンス)」状態を明確に区別して保有しているのである。
態度変容の触媒としての不安定性
アンビバレンスが生じさせる不快な緊張感は、認知的不協和と同様に、解消への動機付けとしてはたらく。しかし、認知的不協和が行動と信念の矛盾から生じるのに対し、アンビバレンスは信念体系内部の矛盾である。
社会心理学の研究では、アンビバレンスが高い状態にある個人は、その不快な葛藤を解消するための情報を積極的に探索し、精緻に処理しようとする傾向があることが示されている。これは、固着した一方的な態度(確信)を持つ人物よりも、アンビバレンスを抱える人物の方が、外部からの説得や新しい情報に対して受容的であり、態度変容を起こしやすいことを意味する。マーケティングにおいて、消費者に製品の「長所」と「短所(高価格など)」を同時に提示する両面提示が有効なのは、意図的に軽度のアンビバレンスを引き起こし、深い情報処理を促すためであるとも解釈できる。
現代の複雑系における適応戦略
近年の意思決定科学の視点では、アンビバレンスを単に解消すべきネガティブな状態としてではなく、複雑な環境に適応するための「賢明な保留」として再評価する動きがある。
現代社会のような不確実性が高く、正解が一つに定まらない状況下では、対象を単純に「善」か「悪」かで即断することは、バイアスによる誤謬のリスクを高める。相反する視点を同時に保持し続ける能力(ネガティブ・ケイパビリティ)は、拙速な判断を避け、多面的な情報を統合してより質の高い意思決定へと至るための高度な認知機能の現れである可能性がある。トップレベルの経営判断や交渉の場において、あえてアンビバレンスな状態に留まり続けることは、状況の変化に柔軟に対応するための戦略的な「遊び」として機能する。
最終更新日:
