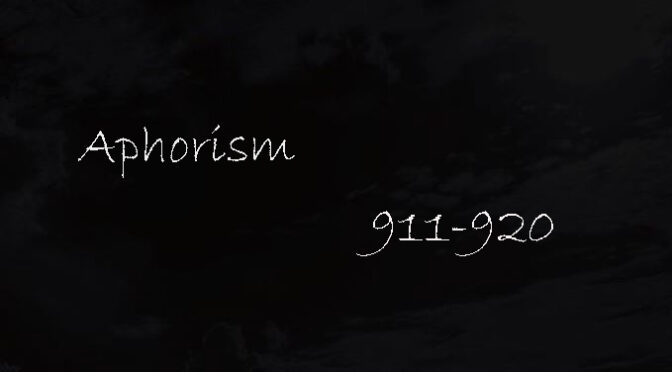アフォリズム 911-920
- 911.事件に対する底意
- 912.丸投げによる解放と教義
- 913.森林浴
- 914.引っ張り合いをやめること
- 915.情報汚染
- 916.爆睡のすすめ
- 917.自覚症状がなくても
- 918.関心と意識の向き
- 919.睡眠不足にある者の態度
- 920.穏やかさへの評価
911.事件に対する底意
社会において重大な事件が起こった時、ものによっては躊躇いや落胆、悲哀を感じながら、どこかしら「これで多少の歪みは矯正される」というような感想を抱いている。
912.丸投げによる解放と教義
あらゆる思考の活動を停止し、一切を放棄して責任を丸投げする。
そうしたものによる解放と自然な現象の最適化の構造があるにしても、その構造と何かしらの教義を結びつけるというのは思考の範囲であり誤謬である。
913.森林浴
ある程度の時間森を歩くと、勝手に精神は安らいでいく。
するとそれに伴うかのように、解決されていないはずの問題が勝手に解決する。「問題ではなかった」という気づきの場合も含めて。
914.引っ張り合いをやめること
思考によってお互いが引っ張り合うよりも、互いに心身を緩める方が根本的な解決に向かう。
相手の考え方の問題が歪んでいるように見えるのは、自分や相手の副腎が疲れていたり腸が荒れていることによる、という場合がある。それは一つの精神による身体への表現である。そして身体の状態が精神に影響を及ぼす。
無理に論理を引っ張り合うよりも、互いの心身を緩める方が先決である。
915.情報汚染
子どもや高齢者が感情を暴走させ抑制が効かなくなるのは、情報処理の能力を超えた情報を浴びてしまうことによる。限定的な領域にのみ、連続して情報をもたらすということが、頭を狂わせていく。
例として連続した動画視聴は、中毒症状を起こし、禁断症状をもたらす。これは奇声を発する要因の一つであるとも考えられる。
これが一種の傾きであるのならば、逆への傾きをもたらせば良い。
それは五感に強い物理的臨場感をもたらすということである。
端的には、自然に触れて体を動かすということである。山を登ったり海で泳いだりということはわかりやすい例である。
できるだけ禁断症状が出なくなるまで、連続して行う方がいいだろう。
916.爆睡のすすめ
「これくらいの睡眠時間でも大丈夫」などどは思わずに、思いっきり寝るべきである。
本当に睡眠時間が足りているのであれば、「どこまでも眠り続けて良い」と言われても、いつも通りの睡眠時間で起きることになる。
寝れるだけ寝ていいという環境になると、たいていの人は貪るように寝る。この場合は、つまり睡眠が足りていなかったということになる。
大丈夫というのと、最高な状態というものは全く異なるのは当たり前じゃないか。
917.自覚症状がなくても
特に腹が痛いというわけでなくても、多少なりと腸が荒れている場合もある。痛いというのが異常であることは間違いないが、痛くないからといって完璧な状態であるとは限らない。
では、何をもって良しとするのか。
それは大きなお便りを見ればすぐにわかる。
918.関心と意識の向き
「今こんなことに関心を向けている自分の意識の向きは、多少なりとおかしいのだろう」という自覚が、向きの修正につながる。
それが確かに社会的な問題であるにしても、絶好調の時は、そんなことに関心を向けすらしない、という構造になっている。
そんな場面はなかったかを思い出した方がいい。
919.睡眠不足にある者の態度
睡眠不足にある者に対して、まともな態度が返ってくるということを期待してはならない。
その度合いにもよるが、「嫌なことがあってやけ酒を浴びた酔っぱらい程度」であると思っておいた方が無難である。
920.穏やかさへの評価
今、穏やかであるのならばそれを存分に評価すべきである。
日々、あれこれ考えうる問題を解決したい、目標を達成したいと思うのも、結局その穏やかさのためにと、思考がもたらしているに過ぎない。
その穏やかさが今あるのに、あえてまた心に波風を立たせるなど、馬鹿げているとは思わないか?
最終更新日: