
解決策へのノイズ
「ようやく浦島太郎から最先端まで追いついた」どころかその先まで行き着きました。様々な違和感の正体は、現代特有の意志決定のプロセスの変化にありました。 単純と言えば単純でした。 ただ、現実への適用は様々な方法を考えて調整していく必要があるなぁとは思っています。 個人的に一番取り戻した感覚としては、ミルトン・エリクソン的な部分です。これは技法等々そうしたものではなく情報の観察力と調整能力です(ああ戻ってよかった良かったと思っています)。 最

第2300回投稿記念
これで2300記事目になります。ブログ創設から2300回目の投稿ということで「第2300回投稿記念」です。 前回の第2201回投稿記念は、2024年7月10日だったので、前回からの99記事は、1年2ヶ月ちょっとかけて投稿したという感じです。またローペースですね。 さて、常連さんいつもご高覧ありがとうございます。 また、contactからご連絡いただいた方、投稿にコメントをいただいた方、ありがとうございます。毎度のことながらたくさんの気づ

僕が最も恐れるものとエネルギーの浪費
僕が最も恐れるもの、それは、自分の中の「怒り」です。自分の中にあるエヴァンゲリオンの暴走のようなものをどうやって抑え込むかということに日々大量のエネルギーを浪費しているフシがあります。 特に外にはないんです。一応世間的に、変な人を避けるとか実りのない争いに巻き込まれないように的な恐れのようなものは、生命維持レベルでありますが、基本的に外の世界に恐れるものはないんです。 一番恐ろしいのは、自分の中でエヴァンゲリオン初号機の暴走のようなこと

変性意識と情報処理能力の限界
変性意識というのは、現実世界への臨場感よりも別の仮想空間への臨場感が強い状態なので、厳密に言うと常に変性意識状態です。ただ、ここでは深い変性意識状態、いわゆるトランス状態について触れていこうと思います。 そして、そうしたものと近年の情報処理能力の限界を超えた人たちについても触れていきます。 一応補足資料としては新規謎コーナー「AIとの対話」に置いてあります。 AIが人間に与える意識変容(変性意識) 本当の脱変性意識状態は、阿羅漢しかたど

ロック&コメディ
あまり不足の方に目を向けるのもどうかと思いますが、現代に最も不足しているものはロックとコメディだと思っています。 最近、久々にビジュアルバムを少しだけ観ました。あとごっつの「サニーさん」などを観たりしています。僕達世代は小学校時代から「ごっつ漬け」であり、笑いの基礎部分の大半はごっつでできています。 やはり小中学生の頃に日曜日の夜八時になると必ず何か鬱屈したものがリセットされるような安心感がありました。 そういう安心感は、ここ数年どころ

出すだけ出して出し切る
人の多いところに行くと酔います。人酔いです。 旅行に行った時、大して何もしていないのに疲れます。 商品が多いところ、ショッピングモールのようなところに行くと酔います。 これらは一応「たいてい初めて見るもの」が情報として入ってくるからです。 19歳か20歳くらいの時に本を10冊読むと、それ以上読めなくなりました。大抵は気絶するように眠ってしまいました。 物理的には可能そうでも、短期的に溜めておける情報量には限りがあり、何かしらまとまるまで

情報を揉む
情報を揉むというようなことについてでも触れていこうと思います。 この情報というのは、情報空間であり情報宇宙のようなものです。ちょっとややこしいですが、バイト表現されるような情報とは少し違います。 思いっきり哲学テーマを書こうと思う時もあるのですが、まとまった時間とそこそこの体力が残っていないと中途半端になるのでしばらくは出せずじまいです。 ただ、何となくちょっとだけ触れていこうと思います。 意識の向きを調整する 「意識の向き」というもの

物事の極端さや中途半端さ
何となくですが、近年は物事が極端です。 いや、別に近年に限ったことではないのですが、特に最近はそんなことを思います。 ある意味で中途半端な感じもします。 様々な業界で人手不足ですが、それほど豊かであるというわけでもありません。使える人材が偏っているというような感じでしょうか。 働いたら働いたで長時間労働になり、そうでなければかなり薄給になるということも極端です。 独り身なら独り身で時間とお金を持て余し、家族がいたらいたでカツカツになる、

残暑の音色
音楽テーマかなと思いつつも乱文的雑記にしようと思います。 最近盆が過ぎたからか、ラジオからフジファブリックがよく流れてきます。 若者のすべてと茜色の夕日。 若者のすべてに関しては、少し前までは「志村氏の声じゃないバージョン」だったので嫌気がさしていましたが、最近流れてくるのは志村氏の声。 それだけで少し嬉しくなります。 ― 様々なものの原点回帰を感じます。 意味不明な偏りを経て、結局元通りに戻っていくような、そんな気がしています。 ―
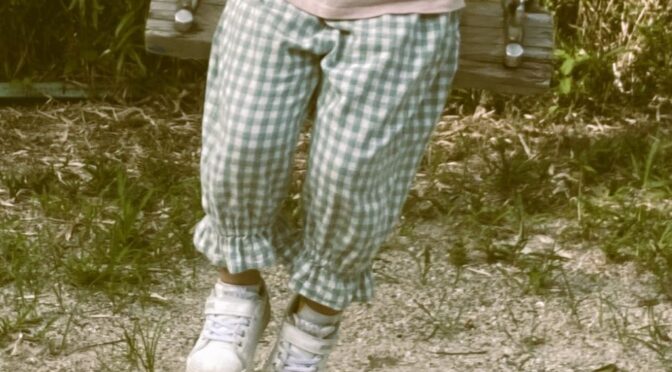
思わぬ角度からもたらされる爆笑
先日、ちょっとだけ連投した時に、本当はもう一つくらい投稿する予定でしたが、「寝かせたほうが面白いだろう」と思ってあえてやめておきました。 で、その内容を書くのかというと、それもまた違います。 「それが吹き飛んでしまった」というのが事実です。 何となくですがその前日まで、どこかで「相手の方がよく知っているだろう」というような萎縮があったような感じでした。 AI(人工知能)・LLM(大規模言語モデル)関連であったり不動産・金融関連であったり

意図を阻害するもの
本来は意識の向きや意図に沿って面白い現象が次々に起こっていきます。 ただ、こうした意図を阻害するものがあります。 意味のあること、役に立つこと、何かをした気分になるもの… 判断の上でおこる様々な基準、それらはすべて基本的には意図を阻害するものです。 「学習は意味のあることだから重要である」ということで向いていないことでもやらされます。 「それは人の役に立たないことだからやめておきましょう」といって何かの意図が妨害されます。 そしてよくあ

朧気ながら見えつつあるもの
最近同じようなことを思っている人によく会います。 結局、相手が答えを持っているわけではないのですが、現在の自分の思考が客観的に見えます。 そうなると、もう八割程度終わったようなものです。 とにもかくにも今現在の体験を全力で感じることが大切です。 瞑想的に集中を高めすぎると日常生活を送ることが難しくなります。 なので、今現在の体験を全力で感じるということが日常との折り合いの中では最も適しています。 それこそがエントロピー増大への対抗になり
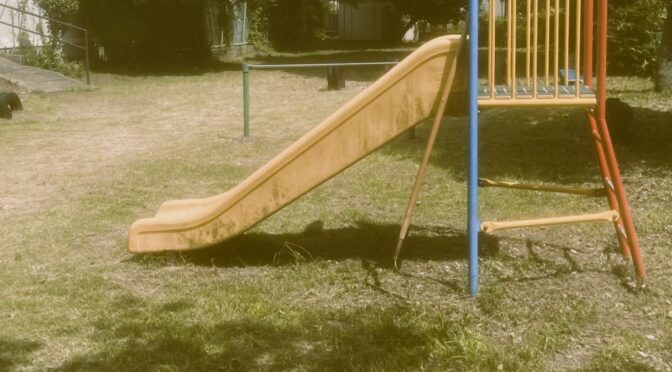
あの日のぼくらの秘密基地
よう、何年ぶりだろう。 覚えてるぜ。 26年ぶりだ。 確か夏だから、本当にちょうど26年ぶりくらいだ。 君はあの時はいなかっただろう。 二代目、ってことになるのかな。 娘を連れてきたぜ、あの子の娘ってわけじゃないけど。 「確かこの辺だったなぁ」と思いつつ、 何度も近くを通っては見逃しまくり。 やっぱり秘密基地だ。 ― 別に何を咎められるわけでもないけど、 大人の目を盗むためにひっそりと。 そんな夏だったな。 関連しているかもしれない記事

好みの作品の隠れた要素
最近、なぜ「ハゲタカ」が好きなのかがわかったんです。 企業の買収が面白いからとか、一時期の自分とハゲタカの時の大森南朋氏がちょっと似てるとかそういう要素もあるのですが、多分そういうのではないんです。 おそらく「嘆いたり、『あわわ』となったり、とにかく頼りない二代目、三代目」を見て笑うのが好きなんです。悪い癖です。 西乃屋の宇崎竜童氏とかサンデートイズの小林正寛氏とかが好きですね。 「そういうタイプの人と深く接したことがあるのですか?」と
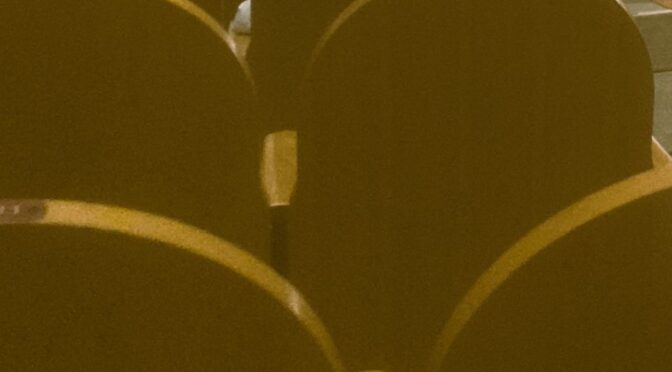
お呼びでないことは百も承知
ずっと感じていた違和感の正体が先日わかったので書き記しておこうと思います。まあ根底にあるものは前々からわかっていたことではありますが、人と話すとどんどん露見していくものです。 幼稚園の行事に参加した時、保護者会会長の挨拶的なものがあったのですが、どうしても前々からその空気感に違和感というか不快感を感じていました。 「非Z会的な空気感からだろうか?」などと思っていましたが、別に友だち全員がZ会というわけでもないですし、数で言えば非Z会の方

現代の思考と頭のゴミ情報による反応的意志決定
「頭のゴミ処理とゴミを宝に変えること」の続編的に現代の思考と頭のゴミ情報による反応的意志決定について触れていこうと思います。 多少なりと普通の人よりは人工知能や自然言語処理等々について触れる機会が多いということもありますが、最近意図的に数種のAIを徹底的に活用しています(というより徹底的に遊んでいます)。 そして現代における思考のあり方がよく見えてきました。 これは個々人の人格の問題ではなく、頭のゴミでパンクしています。 結果、自発的思

スポーツ選手と資本主義
スポーツ選手と資本主義について軽くだけ触れておきましょう。 個人的には我が子にスポーツを本格的にやらせる気はありません。世の中では進学において有利になる的な面でスポーツを推奨しているフシがありますが、仮に何かのスポーツをやってそこそこの才能があったとしても「それを活かして」という発想にならないように、全く手を貸す気はありません。 資本主義においては「その時に利用価値があったから」という程度の評価しか無く、その人の人生のことなど考えてはい

頭のゴミ処理とゴミを宝に変えること
基本的に情報というものは入ってくれば来るほどゴミになります。どのような情報でもたいていはゴミです。ただ、かつて一応の有用性があったものの使用済みとなったためゴミ化していったという感じになっています。 胡散臭い人達の言う「邪気」というようなものは、このゴミです。表現が胡散臭く表現の角度が異常なだけで方向性としては間違っていません。 特に本来の自分には不要な情報、他人の問題に関する情報などはゴミ中のゴミであり、そこに何かしら対応しなければな

情報を触ることと散らかりをまとめること
6月の半ばくらいから僕は本格的に毎日機嫌の良い毎日を過ごしています。 しかしながら、暑さのせいもあるのか周りの機嫌が良くないときがあります。 「知らん」といえばそれまでですが、機嫌が悪い人をよくよく観察してみると、単に意識が散らかっているだけではないかと思ったりもします。 最近特に実感しているのが、傲りでも何でも無く8割以上の人たちにおいて「びっくりするほど頭が良くない」ということです。厳密には頭が回っていないという感じです。別の側面か

一種のタイムライン
客観的に見るとだめなところもたくさんあるはずですが、アメリカはあらゆる面においてずっとトップです。勝手な定義ですが、アメリカが世界で一番であり続ける理由は、単にクリスマスに「It’s a Wonderful Life(素晴らしき哉、人生)」を放映しているからという理由だけだと思っています。 最初に観たときから、次に観るのは死ぬ直前にしようと勝手に決めていましたが、「うーんどうしようかな」と数ヶ月間迷った挙げ句、その禁を破り本

家族を成り立たせようとする子どもの気持ち
家族を成り立たせようとする子どもの気持ちはわかるでしょうか。 両親のどちらのことも大好きで、その関係を成り立たせようと気を使う子どもの気持ち。 親の機嫌が少しでも良くなればと無理をする子どもの気持ち。 「機嫌が悪いのは当たり前だ」というのは居直りの場合があります。 ある時、妻に少し説教のようなことをして、妻が悲しそうな顔をした時、まだ3歳の娘がペネロペのDVDのパッケージを持ってきて 「家族っていいな、家族っていいな」 と、そのDVD「

友人たちの離婚ラッシュから見えるもの
「友人たちの離婚ラッシュから見えるもの」ということで、ここ数年の友人たちの離婚が相次いでいることから、今生きている自分の意識について変な角度から触れていこうと思います。 実際に離婚経験がないのは僕だけで、男女問わず仲の良い友だちは全員離婚しています(その後再婚している例もあります)。唯一親友だけが婚姻を継続していましたが、その最後の一組が先日、離婚成立となりました。 最近会っていない友だちですら年賀状で「息子二人と三人家族になりました」

秘めたる力
本調子どころかさらに力強くなった僕は、物事を強烈に展開させています。厳密に言うと自我としての「僕」が展開させているのではないのですが、主観的感覚としてはそのようになっています。 最近気づきましたが、調子が狂う原因の第一番目は「睡眠不足」ではあるものの、慢性的な「話が通じない人とのやり取り」というものがその次くらいにくるのではないかと思ったりしています。 確か霊長類のボスか何かの事例で、自分の声が群れのみんなに聞こえない=言うことを聞いて

プラネタリウムを観るという夢
先日、妻と娘と三人で青少年科学センターに行ってプラネタリウムを観るという夢を実現してきました。これは昔からの夢です。 娘と青少年科学センターに行くのは二回目ですが三人でとなると初めてです。 ただ、行く前に少し、 「家族みんなでプラネタリウムというのも、冷たい熱帯魚の社本みたいで嫌だな」 となりましたが、関係なく向かうことにしました。 青少年科学センターのプラネタリウムに最後に行ったのは20代の時、プラネタリウムそのものは10年ほど前に滋

情報のかたまりとの付き合い
情報のかたまりとの付き合いについて触れていきます。 結局意識の向きだけで経験することは決まっていきます。 経験に思考も感情も関係はありません。 ある情報のかたまりに意識の向きを向けると、比喩的に表現すればエネルギーを吸い取られます。 そして、その情報のかたまりは何もしてくれません。 それそのものの意志の方向があるだけです。 たまに同調していると、嬉しさや楽しさを経験させてくれることがあります。 しかしそれに飲み込まれてはいけません。 夜

日々のリズム
先日起業家モードに突入してから、「おやおや怪しいぞ」と思って近くの内科に行くと 「過労です」 と言われてしまいました。 「とにかく寝てください」 という指導を受けました。 なので最近は早く寝ています。 「眠れないと時間を無駄にしているようで腹が立ってくるんです」 というようなことを言うと 「きちんと寝て日中にものすごく動いてください」 と言われてしまいました。 なので短期的にデエビゴ等々を服用しています。 昔からモードが切り替わると体の

ぼーっとして固まった思考の動きをリセットする
「ぼーっとするな」というようなことを言う人がいます。 確かに何か仕事をしているときなどは、別のことに気を向けてもらっていては問題が起こります。 しかし具体的な何かに意識を集中していると、そればっかりに考えが集中してしまいます。 気がかりなことがたくさんあると、それらについても考えてしまいます。 そのような時は、徹底的にぼーっとします。 その極みがサマタ瞑想やヴィパッサナーです。 これはパソコンで言うところの再起動に近いような感じです。
白詰草の花冠
お金がなくて、売るものもなくて、近くに生えていた野草を摘んでちょっとした花束にして「誰かが買ってくれないだろうか」と思うようなイメージが浮かんでくることもあります。 それはそれでいいんです。 それをちょっとした飾りにしたら、お店に人が入ってくるだろうか、なんてな期待をするというのもいいんです。 「ああ、お金にはならないか」と諦めるというのもいいんです。 「人を喜ばせた分だけお金が入ってくる。とは言うけどさ」 なんてな気分もいいものだと思

一切の期待を手放して命がけで逃げる
一切の期待を手放して命がけで逃げる、逃げるなら本気で逃げるということをしてみるとよいのではないかと思う時があります。 逃げると言っても何かしら期待を持っている時は本気で逃げてはいません。 本気で逃げるとどうなるのかというと、そのうち意識が「なんでも来い」というような方向に変わります。 しかし、「意識がそうした方向に変わったら改めて取り組もう」などという期待はしてはいけないという格好になっています。 先にそれを期待して、ひとまず逃げるとい

やわらかな陽の中で
陰と陽が統合された感覚を得てから、法人設立当時の感覚が続いています。何かしらの結果が出ても出なくても楽しいような感じですね。 そしてやたらといろいろな人とよく接するようになりました。 宅急便のお兄さんにすら「集荷の電話受付がAIのやつになってましたね」などと声をかけたりしてしまいます(ちなみにAIのやつは何も便利なものではなく、時間を浪費する感じです。お兄さんも「評判悪いですね」などと言って帰られました)。 一方、変なお客にもたまに当た
