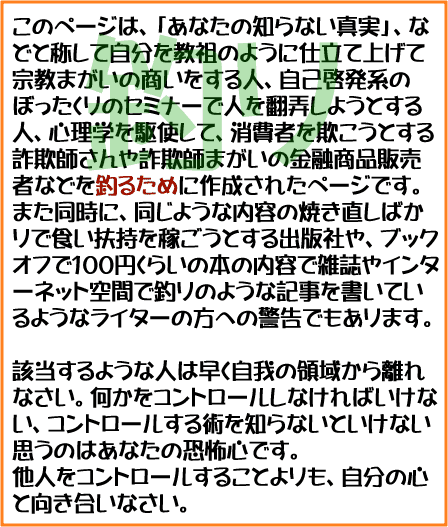
リンゲルマン効果(Ringelmann effect)とは、社会的手抜き現象を意味し、一人で作業する場合と、たくさんの人で作業した場合を比較した場合に、一人あたりの作業量が低下する現象。作業を行うメンバーが増えれば増えるほど一人ひとりの出す力は弱まっていくというような効果である。
このリンゲルマン効果はいわゆる「綱引きを一対一でやった時と集団対集団でやったときでは、一人あたりの力の入り具合が低下する」といったような効果であり、「自分一人が行ったり頑張ったりしても仕方ない」という感じでバイスタンダー効果(傍観者効果)と似たような概念である。
「自分一人で営業を頑張っても仕方ない」とか「選挙に行っても自分ひとりの投票行為ではどうせ変わらない」というような心理は、こうしたリンゲルマン効果、バイスタンダー効果が働いていると考えられるだろう。
リンゲルマン効果と生産性
企業においては人を増やせば増やすほど、それに比例して売上が上がると考えがちだが、人が増えていった際には、リンゲルマン効果によって一人あたりの力の出し具合は弱まり、一人あたりの生産力も低下する。
「社会的手抜き」として、人が増えると責任感も分散し、サボり癖が出るからである。
社会的手抜きが起こる背景
社会的手抜きが起こる背景には、責任の分散というものもあるがそれをさらに紐解くと、管理者や観客などの「監督目線の分散」や、個々人の権限の無さによる意志決定の際の混乱(「やっていいのかどうかわからない」など)などが考えられるだろう。
必然的に生産性は低下
関わる人の数と生産力が比例していく、もしくは何かしらの相乗効果によってより高い生産性が生まれれば万々歳だが、特に「作業」の領域においては、リンゲルマン効果によって必然的に生産性は低下していく。
そして同時に、人員を増やして供給を増やしても、需要にはその数とレベルに限界があるので、さらに期待よりも低い水準でしか売上は上がっていかない。その一方で人を雇うと簡単にはクビを切れない上に固定費が嵩むようになるので売上向上どころか事業の継続自体が危うくなったりもする。
リンゲルマン効果・社会的手抜きの対策として、解雇といった人員整理という方法が最も良いが、トラブルが起こりやすいため対策としてはひとまずグループ・チームといった「まとまり」を小規模化していくのが良いだろう。
集団規模とパフォーマンスの逆相関性に関する社会物理学的考察
リンゲルマン効果、すなわち社会的手抜き(Social Loafing)は、集団作業において個人のパフォーマンスが単独作業時よりも低下する現象を指す。これは単なる個人の怠慢やモラルの欠如として片付けるべき問題ではなく、集団というシステムが構造的に抱える「責任の分散」と「調整コスト」が生み出す、極めて普遍的な社会心理学的現象である。組織が肥大化するにつれて生産性が非線形に低下するこのメカニズムを理解することは、チームビルディングや組織設計において決定的な意味を持つ。
綱引き実験における物理的損失と心理的損失の分離
1913年にフランスの農工学者マクシミリアン・リンゲルマン氏が発表した有名な綱引き実験は、1人の時の力を100%とした場合、2人では93%、3人では85%、8人では49%にまで1人あたりの発揮能力が低下することを示した。長らくこの原因は、タイミングが合わないといった物理的な「調整ロス(Coordination Loss)」と、心理的な手抜きである「動機づけロス(Motivation Loss)」が混然としていた。
この二つを鮮やかに切り分けたのが、1974年のアラン・インガム氏らによる巧妙な実験である。彼らは被験者に目隠しをさせ、「他のメンバーと一緒に綱を引いている」と信じ込ませた状態で、実際には自分一人だけで引かせた。その結果、物理的な調整ロスが起こり得ない状況(一人で引いている)であるにもかかわらず、集団で引いていると思い込んでいるだけで力の低下が観測された。これにより、リンゲルマン効果の本質が、他者の存在に依存した心理的な手抜きにあることが科学的に証明された。
社会的インパクト理論と評価懸念の希薄化
なぜ人は集団の中に埋没すると手を抜くのか。ビブ・ラタネ氏が提唱した「社会的インパクト理論(Social Impact Theory)」は、この現象を力学的に説明する。外部からの圧力(期待や評価)は、対象となる人数が増えるほど分散され、一人あたりが受けるインパクトは弱まる。
個人の貢献が特定されない状況では、頑張っても評価されず、サボっても罰せられないため、「評価懸念」が低下する。これがフリーライダー(ただ乗り)現象を引き起こす主要因である。逆に言えば、集団作業であっても個々の貢献度が可視化され、特定可能(Identifiability)であるならば、手抜きは抑制される。現代のプロジェクト管理ツールがタスクの担当と進捗を細分化して可視化するのは、この心理的メカニズムを逆手にとった抑止策として機能している。
集合的努力モデルと期待価値のリンク
スティーブン・カロー氏らが提唱した「集合的努力モデル(CEM: Collective Effort Model)」は、この現象をさらに精緻化し、期待価値理論の枠組みで捉え直したものである。人が努力をするためには、「努力すれば成果が出る(期待)」「成果が出れば報酬が得られる(手段性)」「その報酬には価値がある(誘意性)」という三つのリンクが繋がっていなければならない。
集団作業においては、特に「自分の努力が成果に直結するか」という感覚と、「成果が自分への報酬として返ってくるか」という確信が揺らぎやすい。自分が頑張らなくても誰かがやってくれるかもしれないし、成功しても報酬は山分けになるかもしれない。この認知的リンクの切断が、動機づけの低下を招く。したがって、手抜きを防ぐには、個人の努力がチームの勝利に不可欠であることを認識させ(不可欠性の認知)、かつその勝利が個人にとっても意味あるものであると再定義する必要がある。
社会的補償効果という逆転現象
興味深いことに、集団作業が常にパフォーマンス低下を招くわけではない。ウィリアムズ氏とカロー氏の研究によれば、パートナーの能力が低いと信じている場合や、課題自体が個人にとって極めて重要である場合、人は1人の時よりもむしろ高いパフォーマンスを発揮することがある。
これを「社会的補償(Social Compensation)」と呼ぶ。他者の不足分を自分が補わなければならないという責任感や、集団の失敗を回避したいという強い動機が、手抜きバイアスを凌駕する瞬間である。また、集団の凝集性(まとまり)が高く、メンバー間の信頼関係が強固な場合も、相互の期待に応えようとする作用が働き、リンゲルマン効果は抑制される。つまり、組織の生産性は、単なる人数の多寡ではなく、メンバー同士が互いの存在をどう認知し、どのような関係性を結んでいるかという「心理的結合の質」に依存していると言えるだろう。
最終更新日:
